 歴史・文化
歴史・文化 「神宮」とは?伊勢神宮だけじゃない“神宮”の意味と由来を解説
「神宮」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは伊勢神宮かもしれません。しかし、日本全国・・・続きを読む
 歴史・文化
歴史・文化  旅行・体験
旅行・体験  歴史・文化
歴史・文化 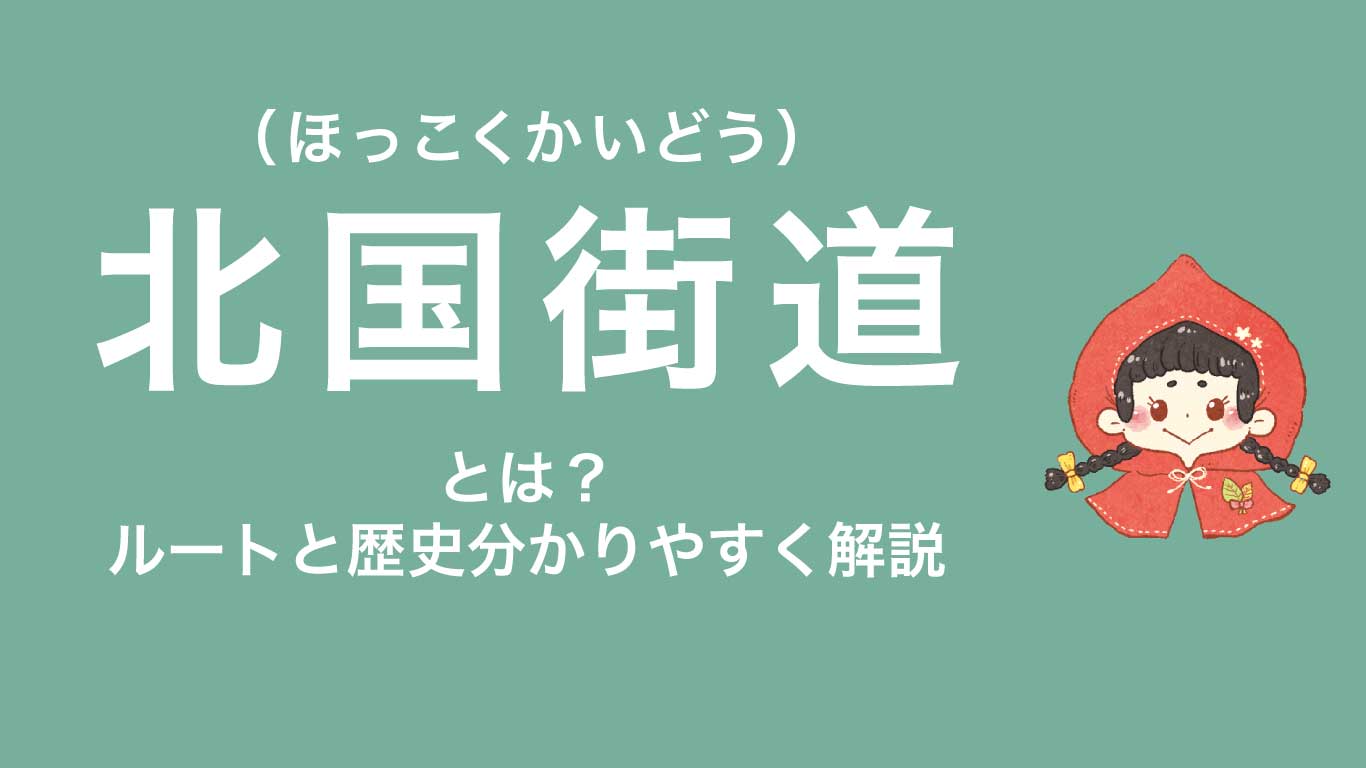 宿場町・街道用語解説
宿場町・街道用語解説 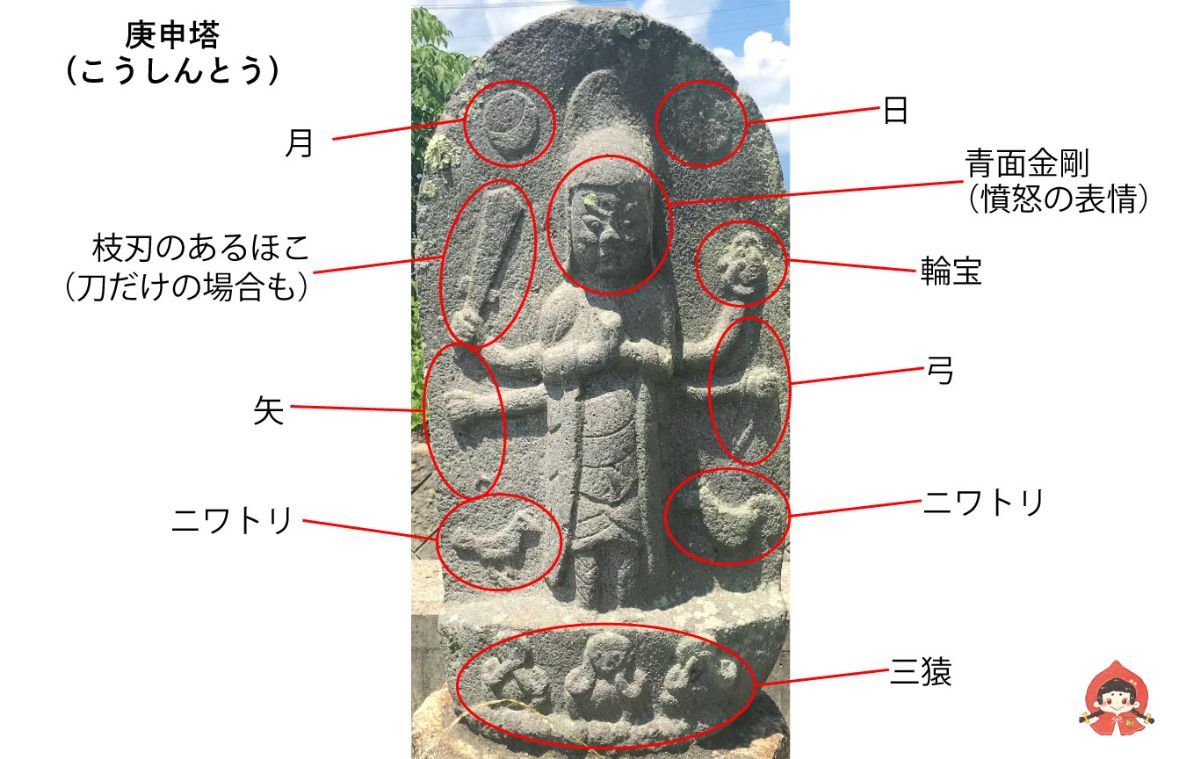 歴史・文化
歴史・文化 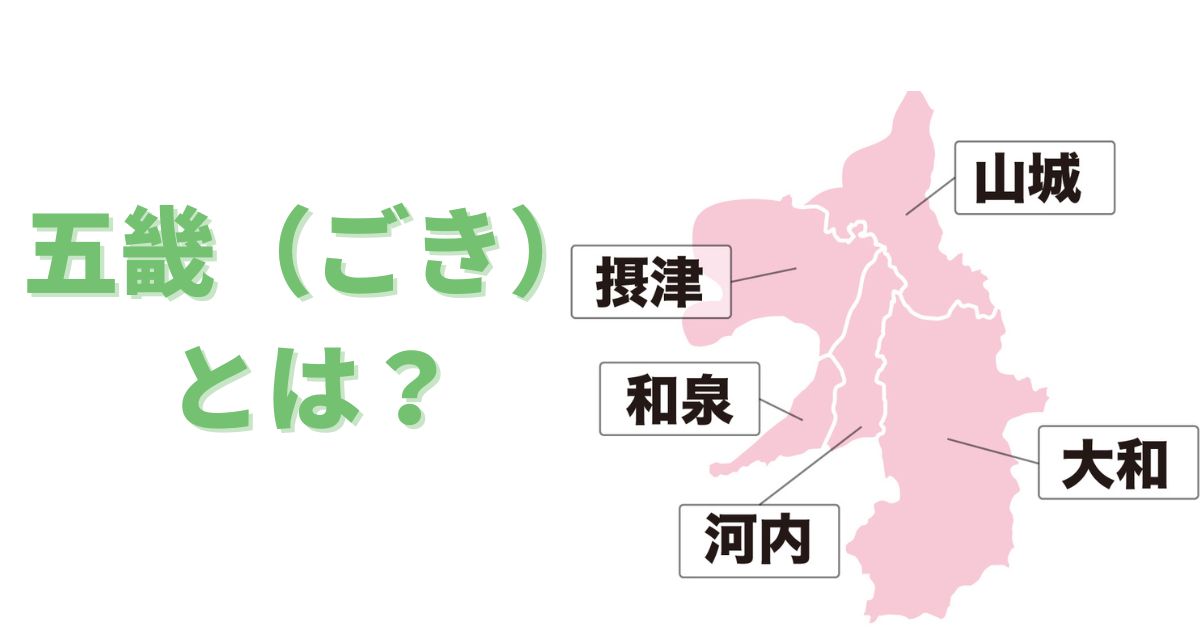 歴史・文化
歴史・文化  街道コラム
街道コラム  街道コラム
街道コラム .jpg) 歴史・文化
歴史・文化  歴史・文化
歴史・文化