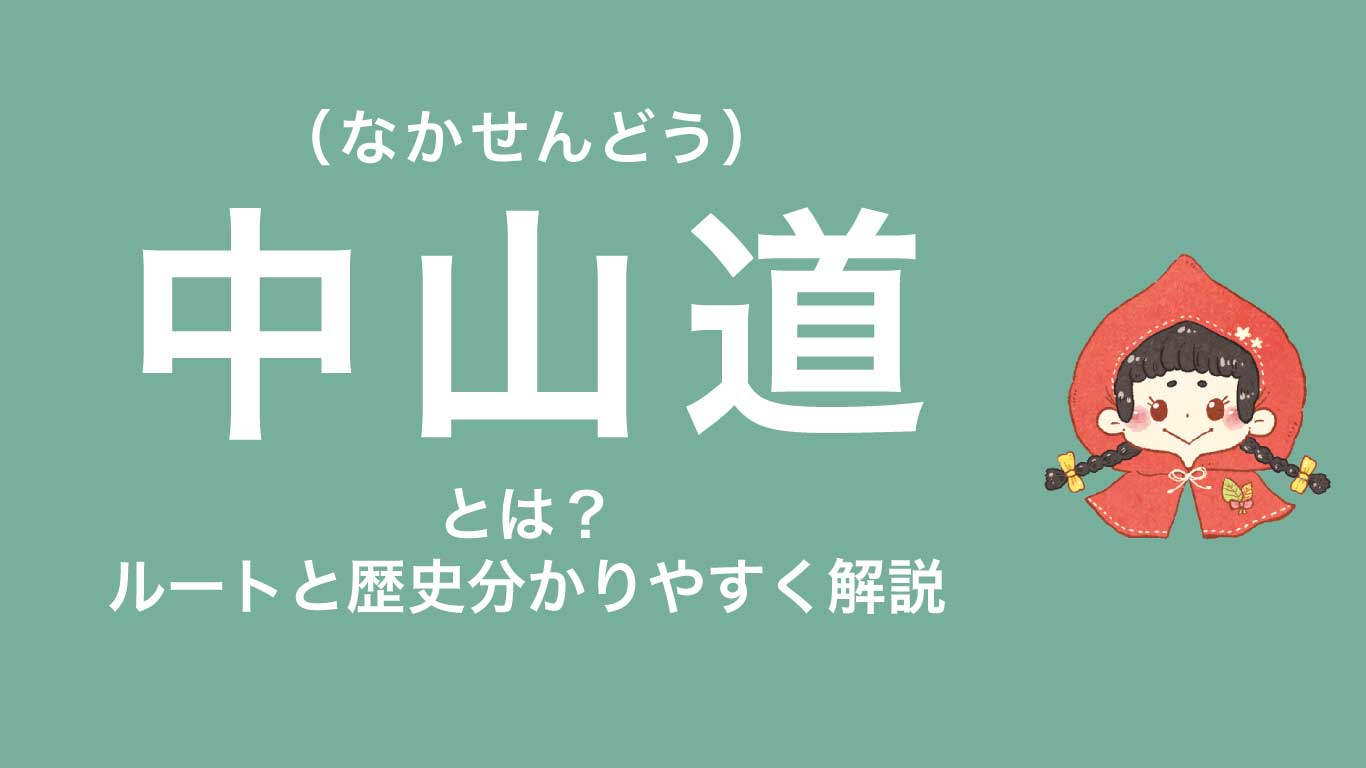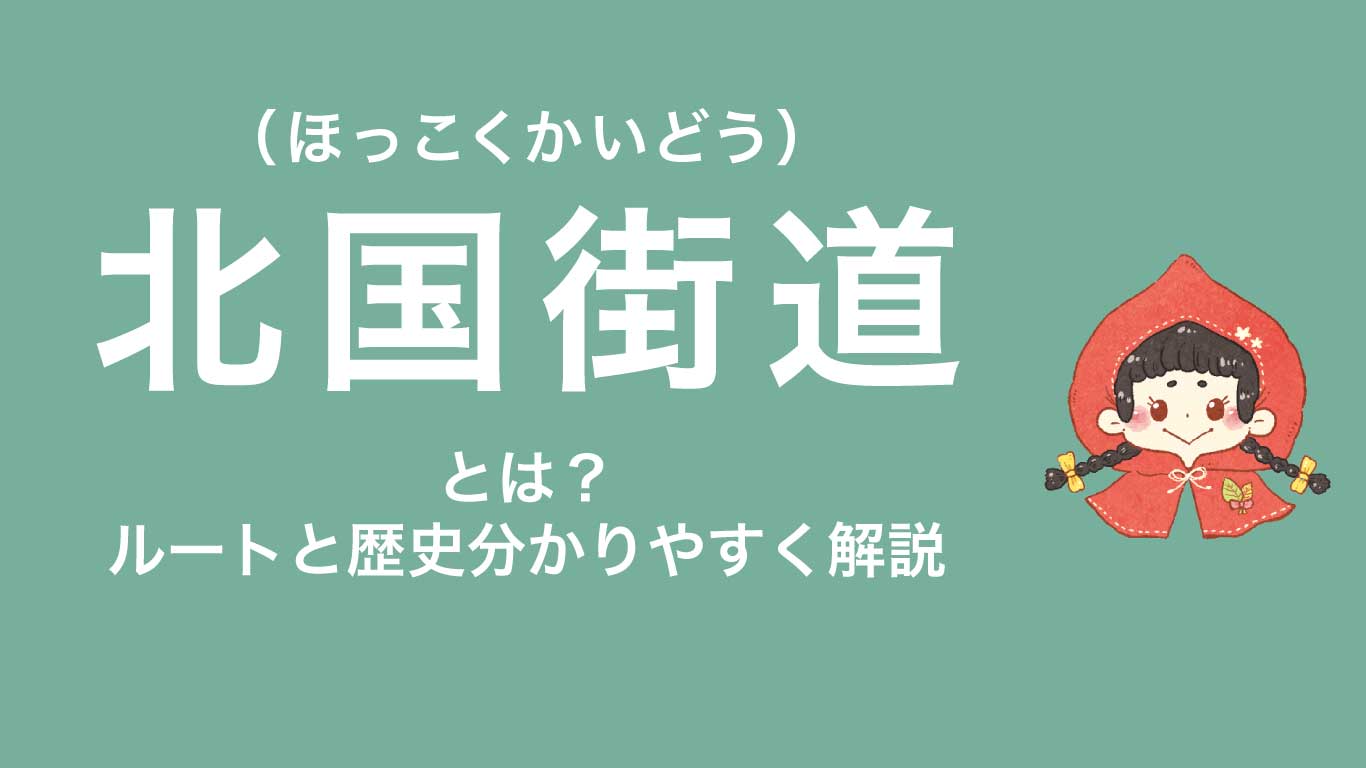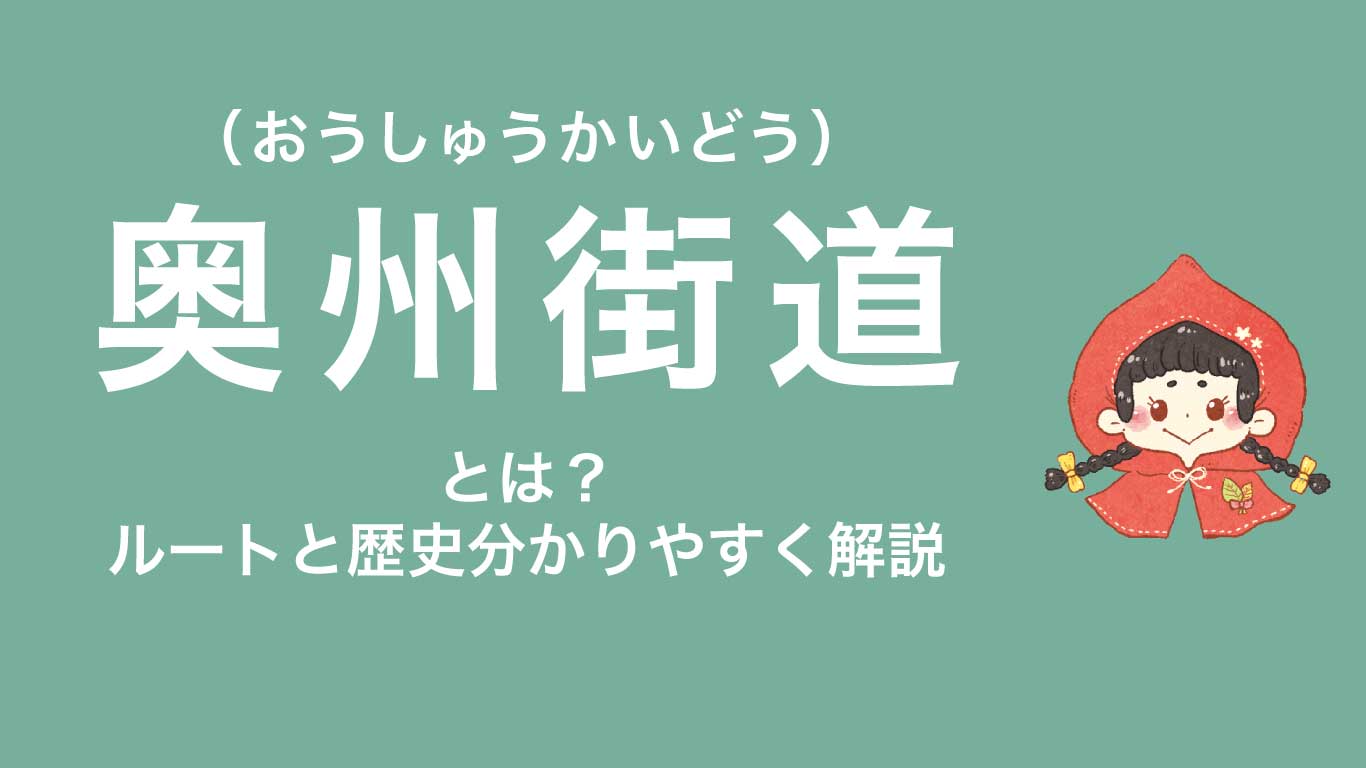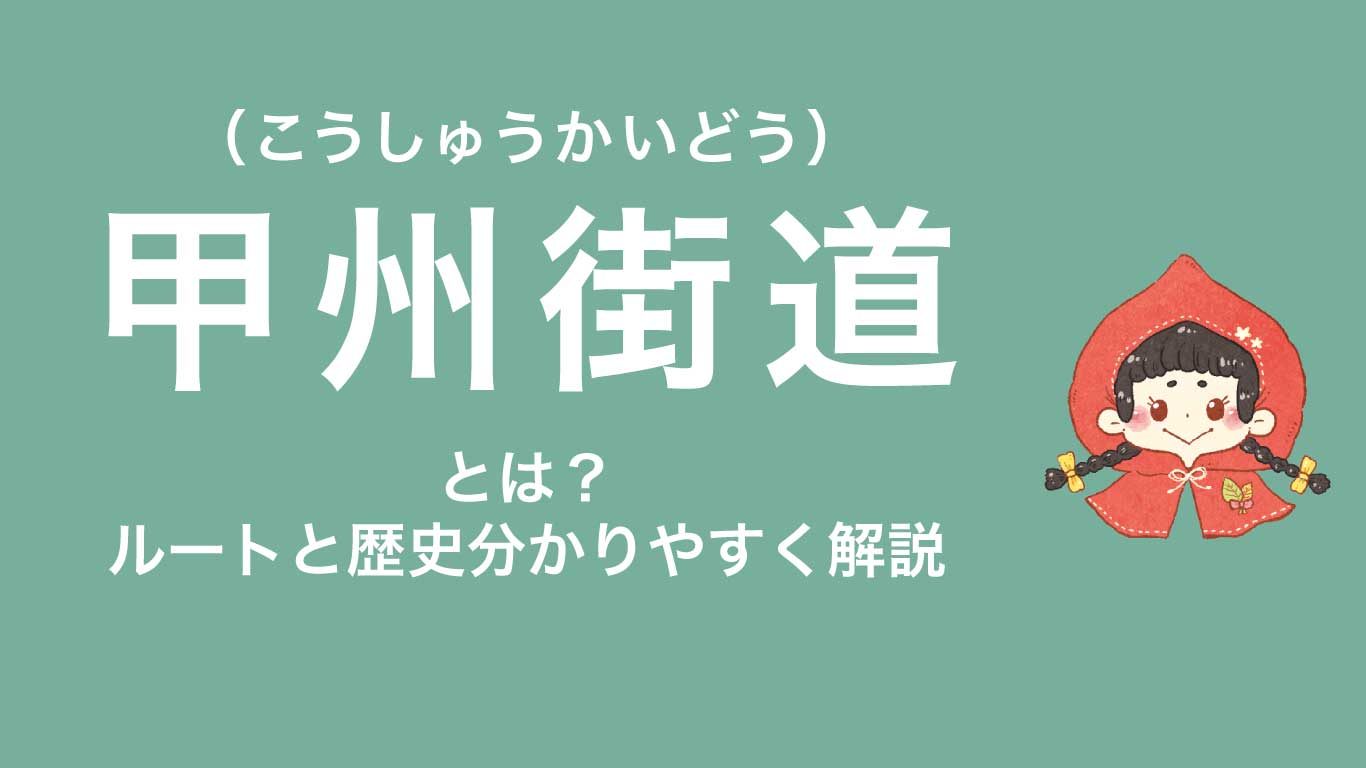現代の日本には鉄道や高速道路、バスなど、移動のための便利な交通システムがあります。では、古代の日本ではどのように人や情報を運んでいたのでしょうか?
その答えのひとつが「駅制(えきせい)」です。律令国家の時代に整えられた交通制度で、中央から地方へ命令や物資を届けるための仕組みでした。今回は、この駅制についてわかりやすく解説します。
駅制(えきせい)とは?

駅制とは、7世紀後半から8世紀ごろに整備された交通制度で、官道(かんどう:政府が整備した主要道路)に一定間隔で「駅家(うまや)」を設置し、人や馬を交代させながら移動するシステムです。
簡単にいうと、「リレー方式で人や物を運ぶ仕組み」で、都から地方まで効率よく連絡を取るために活用されました。
駅家(うまや)の役割
駅制の中心となったのが「駅家(うまや)」です。
- 約16kmごとに設置された中継拠点
- 使者が宿泊できる施設
- 馬を交代させる場所
現代で例えるなら「サービスエリア」や「バスターミナル」のような存在でした。
伝馬(てんま)と駅制
駅制では「伝馬(てんま)」と呼ばれる公用の馬が用意されていました。使者は駅家で馬を替えながら移動し、速やかに都の命令や物資を届けました。
これにより、長距離でも短時間で情報を伝えることが可能になったのです。
誰が支えたのか? ― 伝馬役
駅制を維持するためには、多くの人々の労力が必要でした。地方の農民には「伝馬役(てんまやく)」と呼ばれる負担が課せられ、馬や食料を提供する義務があったのです。
これは重い負担となり、のちに駅制の衰退の一因ともなりました。
駅制の役割
駅制は、古代の日本において次のような役割を果たしました。
- 政治の支配:中央政府が地方を効率よく統治できた。
- 軍事の移動:兵士や物資の移送を迅速に行えた。
- 文化の伝播:仏教や都の文化が地方へ広がる助けとなった。
駅制の衰退
時代が進み、律令制度が形だけのものになると、駅制も次第に維持が難しくなりました。
伝馬役の負担が農民にとって重すぎたことや、武士の台頭で交通の仕組みが変化したことなどが理由です。やがて駅制は姿を消し、鎌倉時代以降は新たな交通制度が生まれていきました。
まとめ|駅制(えきせい)とは?古代日本の交通システムをわかりやすく解説
駅制とは、古代日本の交通と情報伝達を支えた重要な制度でした。
「駅家」や「伝馬」を利用したリレー方式の仕組みは、現代でいう高速道路や鉄道網のような存在です。駅制を学ぶことで、古代の人々がどのようにして広い国土をまとめていたのかが見えてきます。
▼宿場街道のノミチ記事はこちら