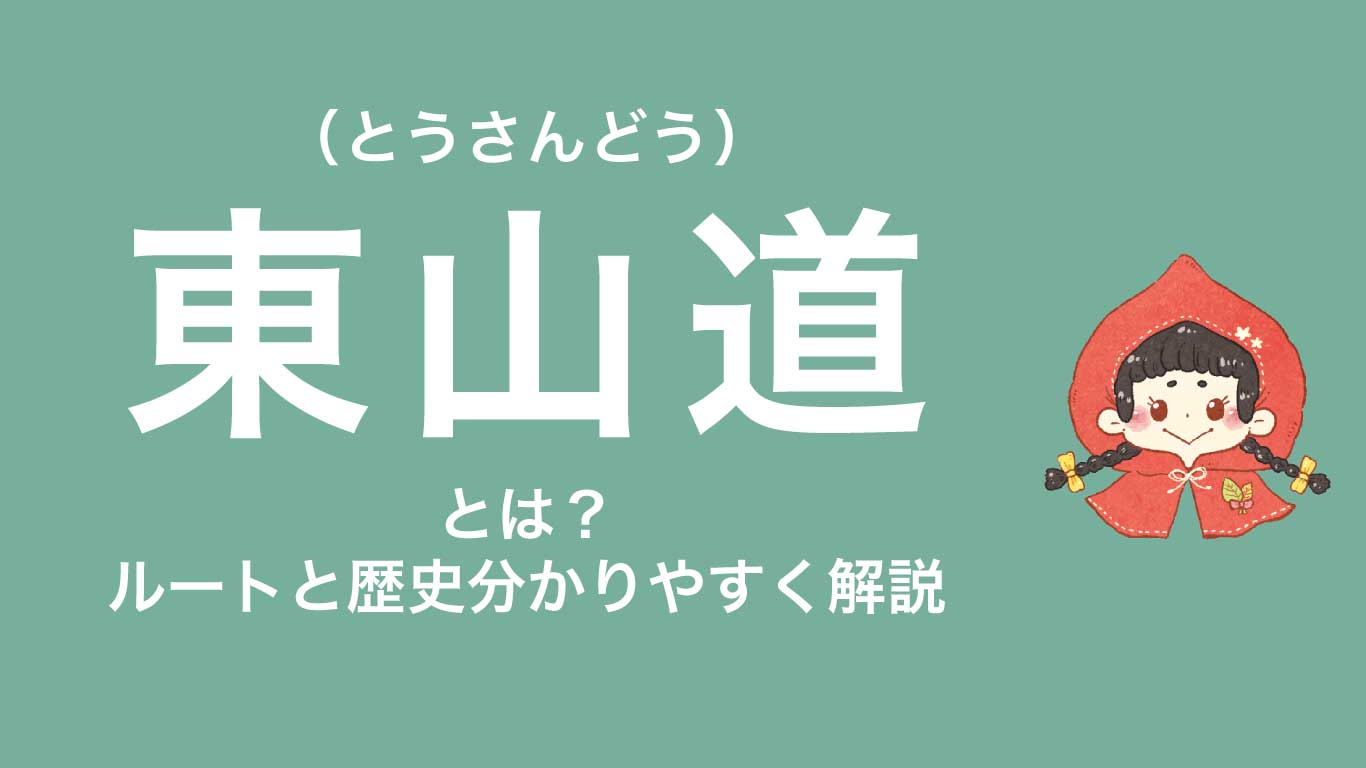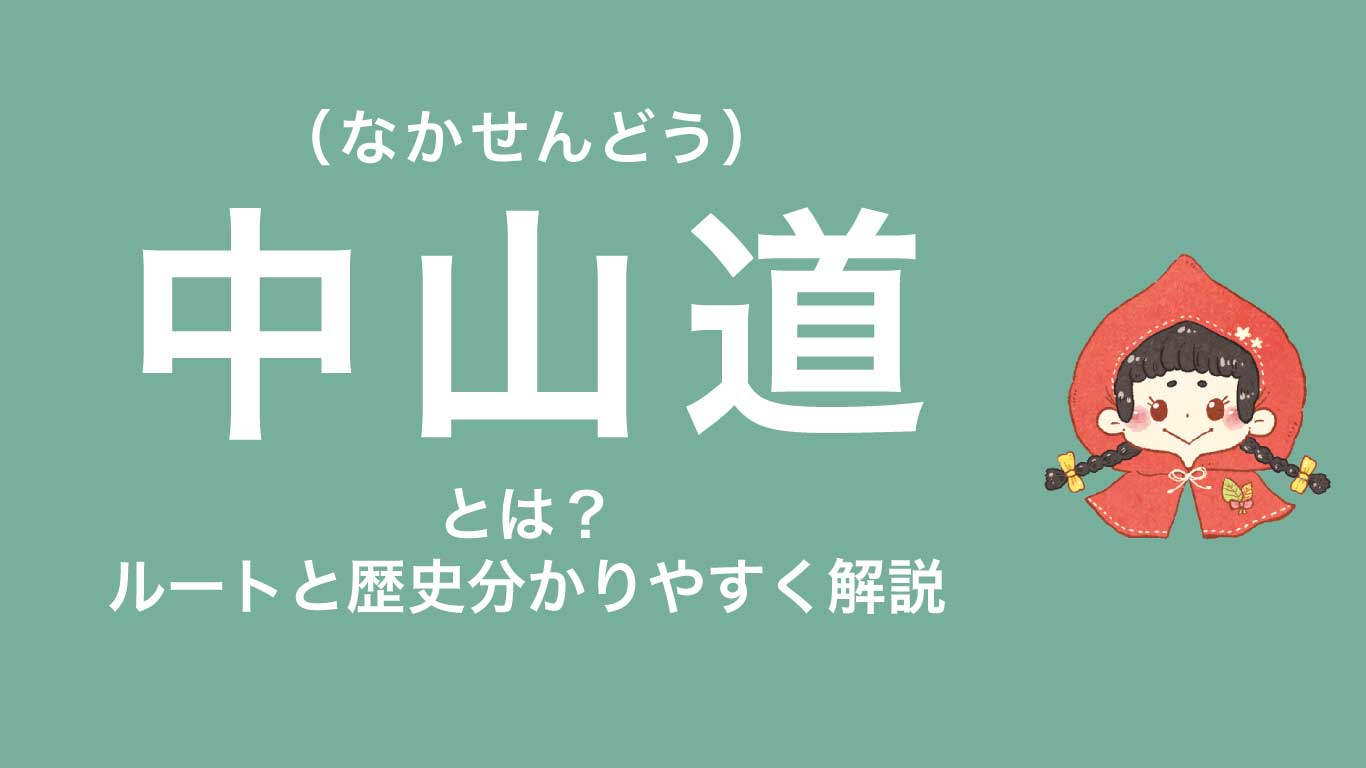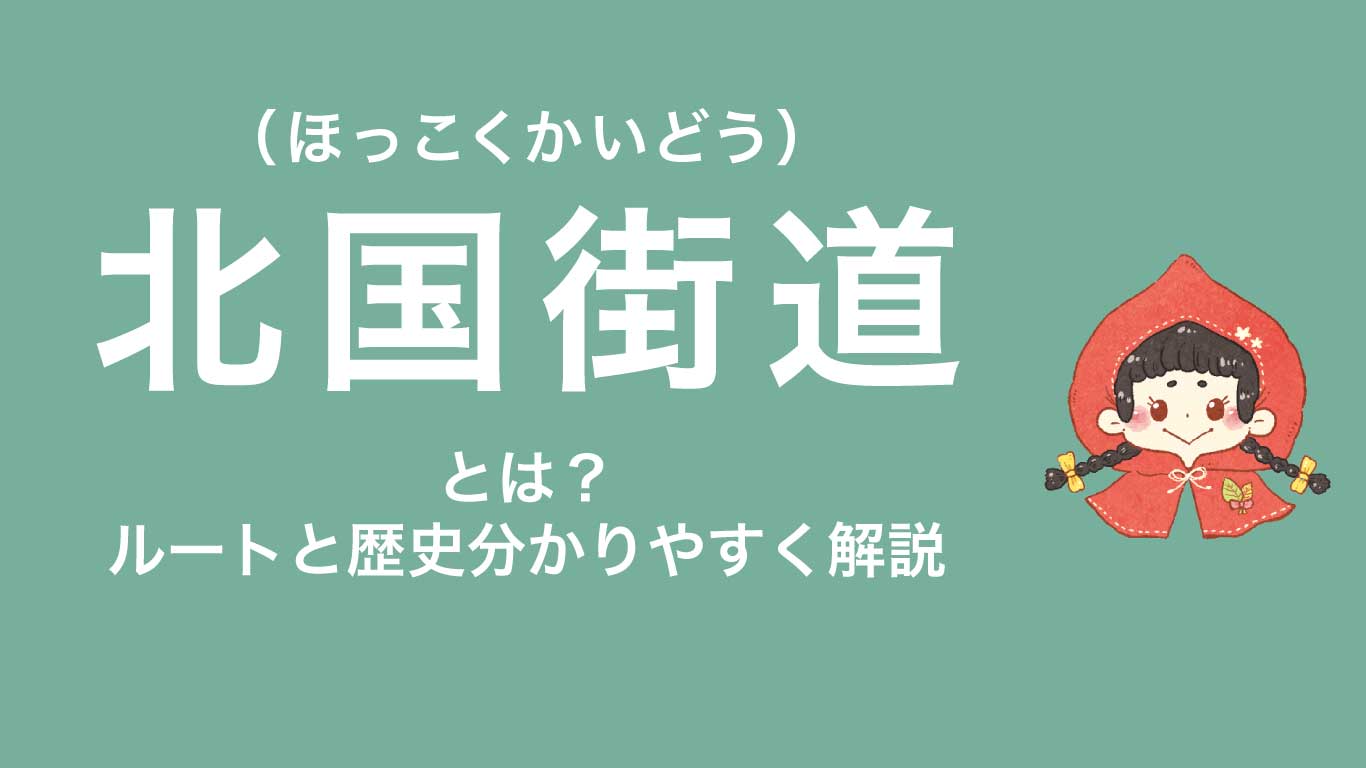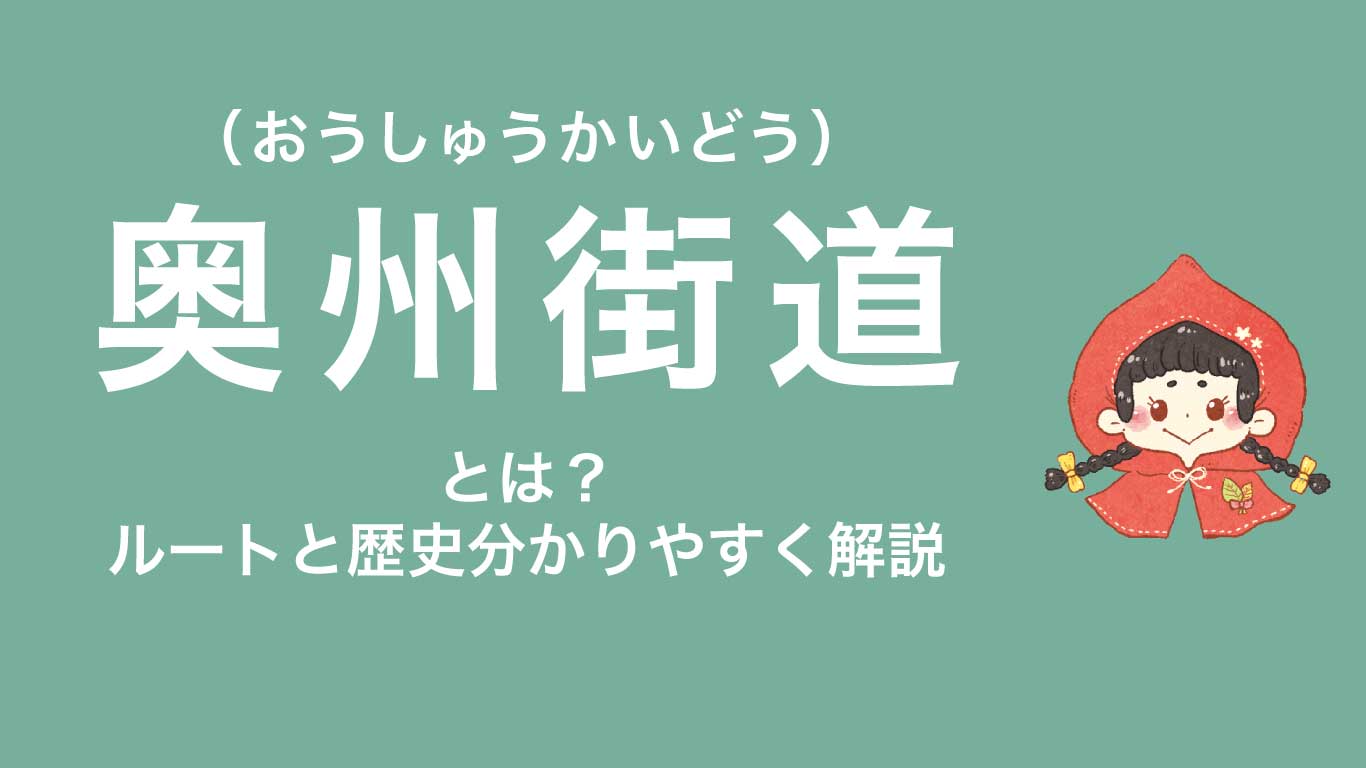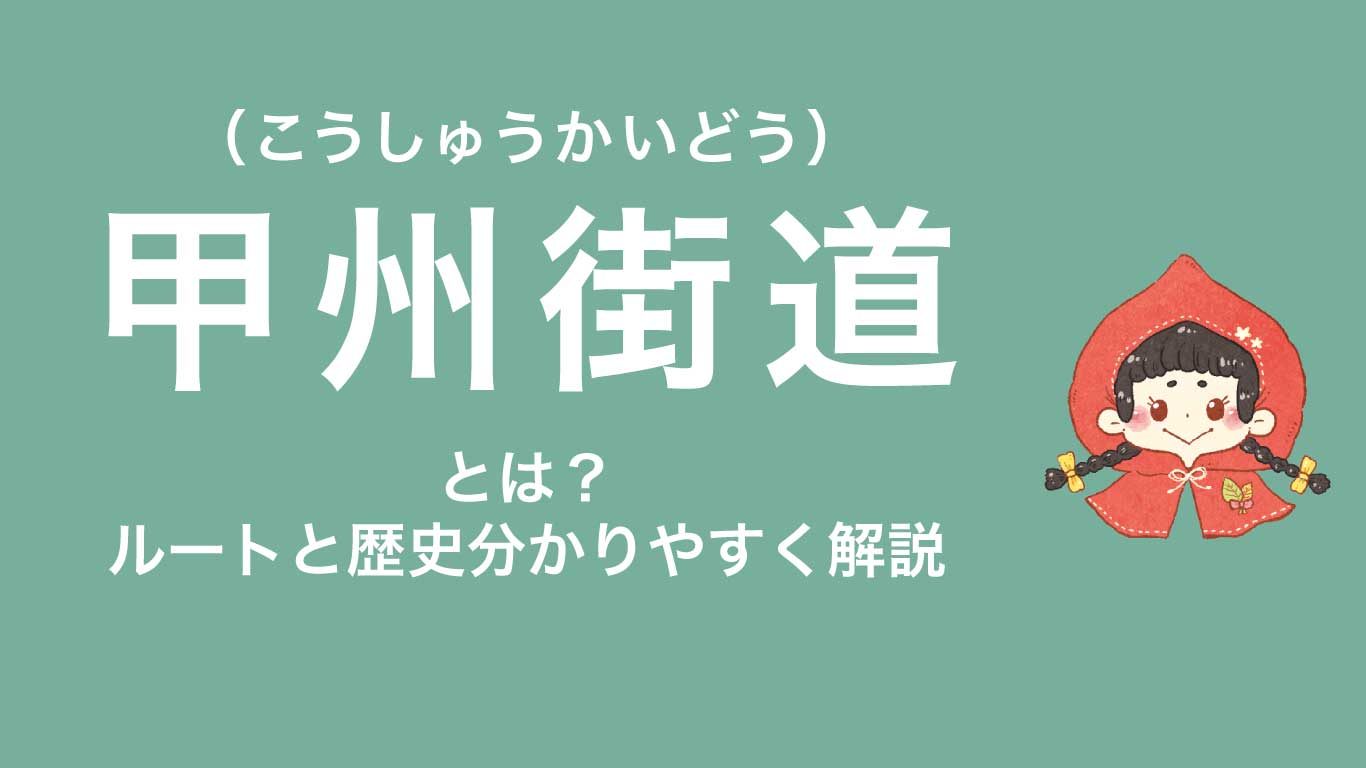古代日本には、都と地方を結ぶ幹線道路網「五畿七道(ごきしちどう)」が整備されていました。
その中の一つが、畿内から内陸部を通り、陸奥国(現在の東北地方南部)まで伸びる「東山道(とうさんどう)」です。
山間部を縫うように通るこの道は、政治・軍事・物流において重要な役割を果たしてきました。本記事では、東山道のルートや地図、沿線の宿場町をわかりやすく解説します。
東山道とは?

東山道は、飛鳥時代から奈良時代にかけて整備された古代の官道で、「東国へ向かう山間の道」という意味を持ちます。都(平城京)から近江・美濃・信濃・上野を経由し、陸奥国の多賀城へ至る内陸ルートで、総延長は約1200kmと推定されています。
奈良時代の律令制では、東山道は交通・通信の動脈としてだけでなく、軍隊や税の輸送にも利用されました。また、古代の道は後世の中山道や奥州街道などの基礎にもなっています。
東山道のルートと地図

古代の東山道は、以下の国々を通過しました。
- 近江国(現在の滋賀県)
- 美濃国(岐阜県)
- 信濃国(長野県)
- 上野国(群馬県)
- 下野国(栃木県)
- 陸奥国(福島県・宮城県)
代表的なルートは以下のとおりです。
平城京(奈良県) → 近江国(大津) → 美濃国(垂井) → 信濃国(諏訪) → 上野国(高崎) → 下野国(宇都宮) → 陸奥国(白河) → 多賀城(宮城県)
※地図化すると、近畿から東北まで日本列島の脊梁山脈沿いを一直線に貫くルートになります。
東山道はどこからどこまで?
東山道は、古代の都(平城京)から陸奥国の多賀城までを結ぶ内陸ルートです。起点は現在の奈良県奈良市付近にあり、近江国(滋賀県)、美濃国(岐阜県)、信濃国(長野県)、上野国(群馬県)、下野国(栃木県)、そして陸奥国(福島・宮城県)を通過します。終点の多賀城は、奈良時代に陸奥国の国府として置かれた政治・軍事の中心地でした。
全長は約1,200kmと推定され、山間部を通る険しい道でありながら、古代日本の東西・南北を結ぶ重要な幹線道路でした。
東山道の呼び方
「東山道(とうさんどう)」の名称は、文字通り「東の山間を通る道」という意味です。古代律令制のもとで定められた五畿七道(ごきしちどう)の一つとして、東海道や西海道と並び称されます。
読み方は「とうさんどう」が正しく、現代の「東海道(とうかいどう)」とは別の路線です。ちなみに、平安時代以降は中山道や奥州街道といった新しい道が整備され、東山道のルートや名称も時代とともに変化していきました。
まとめ|「東山道(とうさんどう)」とは?
東山道は、日本列島を南北に貫く古代の大動脈でした。
険しい山間を越えるルートでありながら、古代の人々は馬と駅制を駆使して効率的に往来していました。
現在ではその多くが鉄道や国道に姿を変えていますが、旧道や宿場町跡を訪ねれば、古代から続く道の記憶に触れることができます。
▼街道用語のノミチ記事はこちら