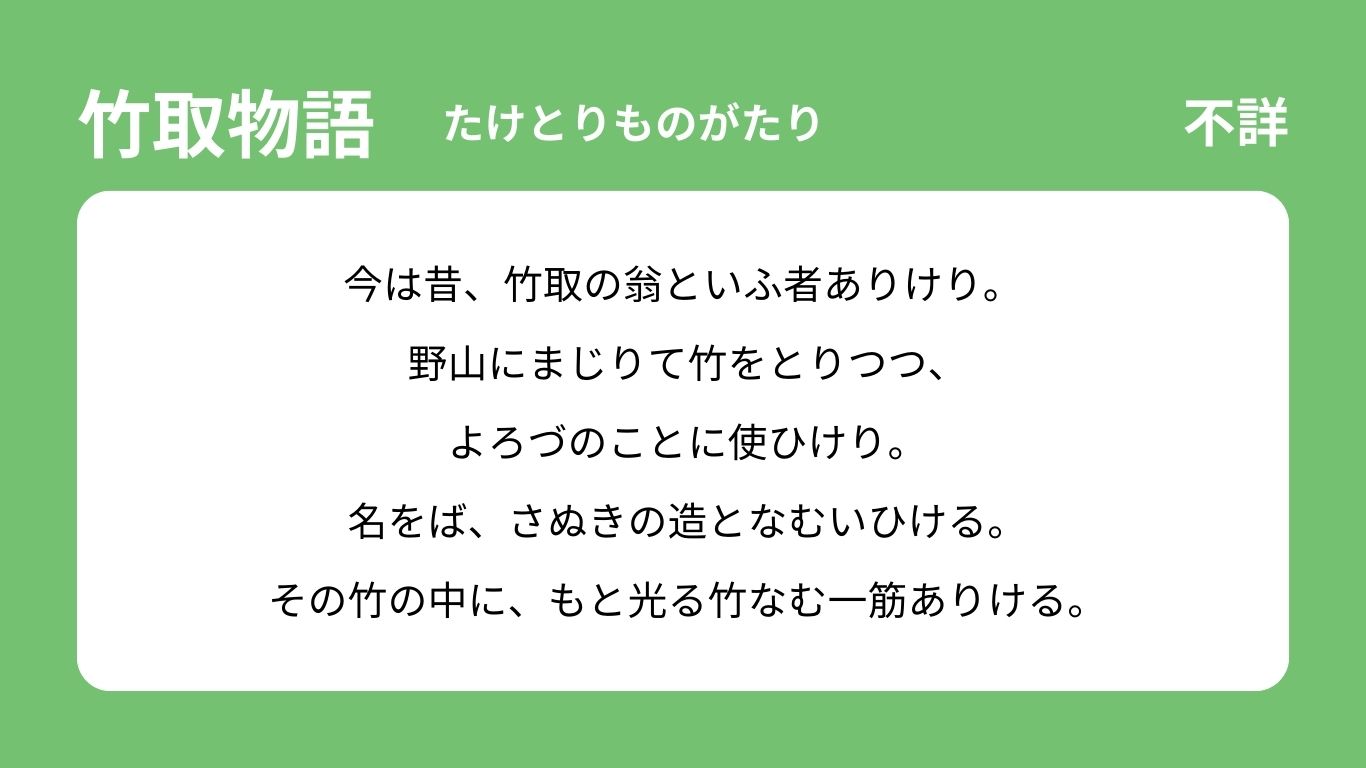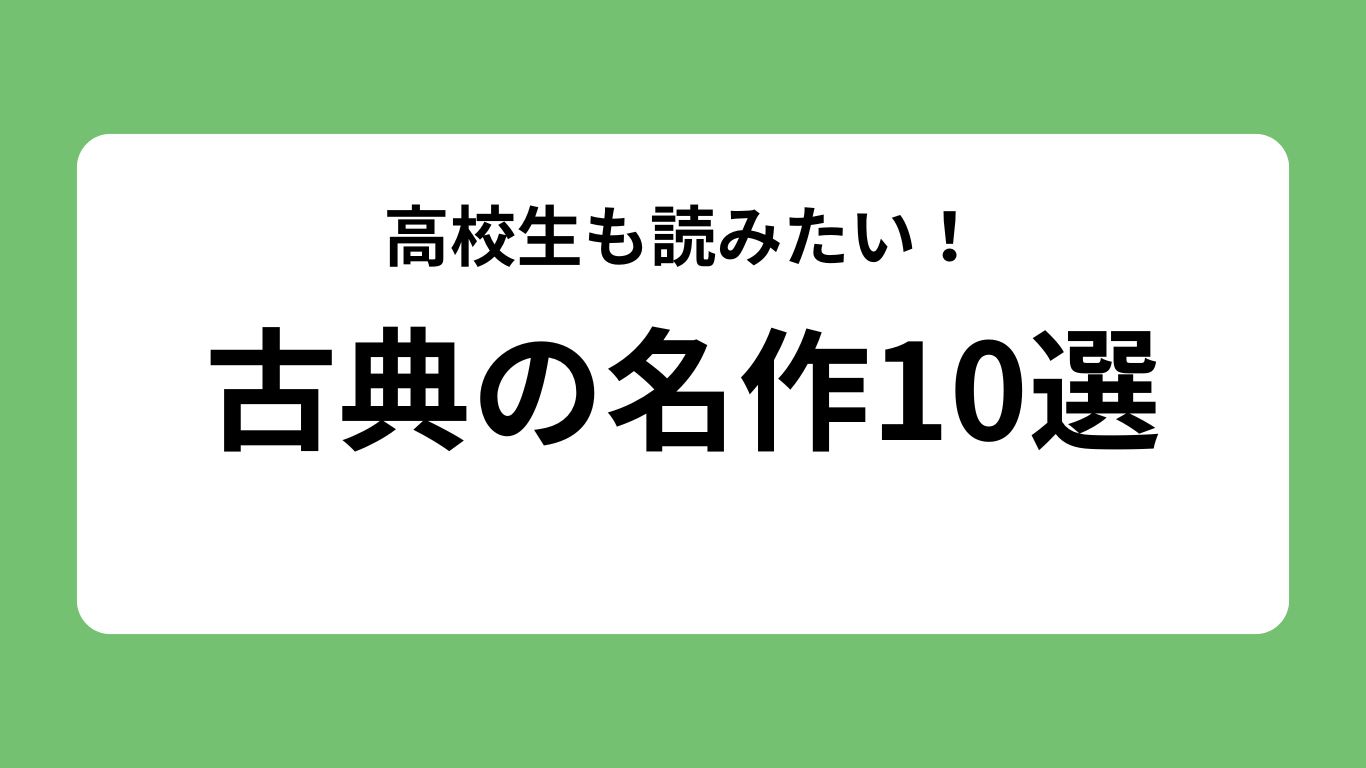月からやってきた“かぐや姫”が主人公の『竹取物語(たけとりものがたり)』。
中学生の教科書にも掲載されており、冒頭文を覚えている方も多いのではないでしょうか。
わたしが最初に覚えた冒頭文であり、いちばん大好きな古典作品でもあります。
今回はそんな『竹取物語』の冒頭文とあらすじをピックアップし、分かりやすく解説いたします。
▼高校生も大人も読んでおきたい古典の名作はこちら!
日本最古のSF小説『竹取物語』とは?
『竹取物語』は平安時代初期に成立した作者不詳の小説です。
「日本最古のSF小説」とも呼ばれています。異世界から来た美少女が主人公だなんて、さすが日本といったところですね!
かぐや姫は月で何らかの罪を犯し、その罰として地球に流されました。月には死や病などがないため、月から見た地球は地獄のようなものだったのかもしれません。
姫の罪とは何だったのか。どんな思いで月に帰って行ったのか。
想像を膨らませる不朽の名作です。
| 名称 | 竹取物語(たけとりものがたり) |
| 作者 | 不詳 |
| 成立年代 | 平安時代初期 |
| ジャンル | 小説 |
『竹取物語』のあらすじ
『竹取物語』のあらすじを簡単に説明します。
竹取の翁が山で竹を取っていると、竹の中から小さな女の子が現れます。おばあさんと一緒に大切に育てると、それは美しい女性に成長しました。
するとかぐや姫に求婚する5人の男性が現れます。しかしかぐや姫はそれぞれの男性に難しい条件を出し、すべての求婚をはねのけてしまいました。
かぐや姫は育ての親であるお爺さんとお婆さんに、自分は月の都からやってきたこと、もうすぐ帰らなければいけないことを告げます。2人はかぐや姫を守ろうとたくさんの兵士たちで屋敷を囲みますが・・。
『竹取物語』冒頭文
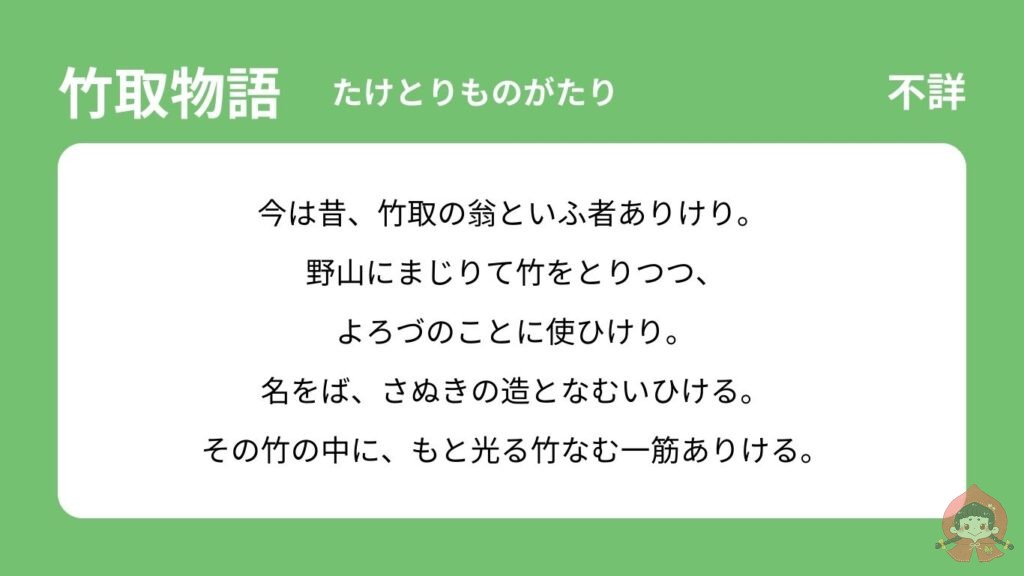
▼冒頭文(原文)
今は昔、
竹取(たけとり)の翁といふ者ありけり。
野山にまじりて竹を取りつつ、
よろづのことに使ひけり。
名をば、
さぬきの造(みやつこ)となむいひける。
その竹の中に、
もと光る竹なむ一筋ありける。
あやしがりて、寄りて見るに、
筒の中光りたり。
それを見れば、
三寸ばかりなる人、
いとうつくしうてゐたり。
▼冒頭文(現代語訳)
今となっては昔のことだが、
竹取の翁という人がいました。
野山に入って竹を取っては、
たくさんのことに使っていた。
名前を、
さぬきの造といった。
その竹の中に、
根本の光る竹が1本あった。
怪しがって寄ってみると、
筒の中が光っていた。
それを見ると、
3寸(約9cm)ほどの人が
とてもかわいらしい様子で座っていた。
『竹取物語』冒頭文の意味と読み方
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
→今となっては昔のことだが、竹取の翁という人がいました。
▼原文と読み方
今は昔
▼現代語訳
今となっては昔のことだが
▼原文と読み方
竹取(たけとり)の翁(おきな)
▼現代語訳
竹取を生業としているお爺さん
野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。
→野山に入って竹を取っては、たくさんのことに使っていた。
▼原文と読み方
野山にまじりて竹を取りつつ
▼現代語訳
野山に分け入って竹を取りつつ
▼原文と読み方
よろづのことに使ひけり
▼現代語訳
たくさんなことに使っていた
名をば、さぬきの造となむいひける。
→名前を、さぬきの造といった。
なむ(係助詞)強調を表します。
また「なむ〜ける」のように終止形(けり)で終わらない現象を「係り結びの法則」といいます。
▼原文と読み方
名をば〜なむいひける
▼現代語訳
名前を〜といった
▼原文と読み方
さぬきの造(みやつこ)
▼現代語訳
讃岐という場所のみやつこ
造(みやつこ)は国主や国に使える役人という意味があるらしいよ!
その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。
→その竹の中に、根本の光る竹が1本あった。
▼原文と読み方
もと光る竹
▼現代語訳
根本が光っている竹
▼原文と読み方
一筋
▼現代語訳
1本
あやしがりて、寄りて見るに、筒の中光りたり。
→怪しがって寄ってみると、筒の中が光っていた。
▼原文と読み方
怪しがりて、寄りて見るに
▼現代語訳
怪しがって寄って見ると
▼原文と読み方
筒の中光りたり
▼現代語訳
筒の中が光っていた
それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。
→それを見ると、3寸(約9cm)ほどの人がとてもかわいらしい様子で座っていた。
▼原文と読み方
いとうつくしうて
▼現代語訳
とてもかわいらしい姿で
美しいというのは、現代の言葉で「かわいらしい」という意味になります。
▼原文と読み方
ゐたり
▼現代語訳
座っていた
1寸は3cmなので、3寸は9cmくらいだね!
『竹取物語』冒頭文 まとめ
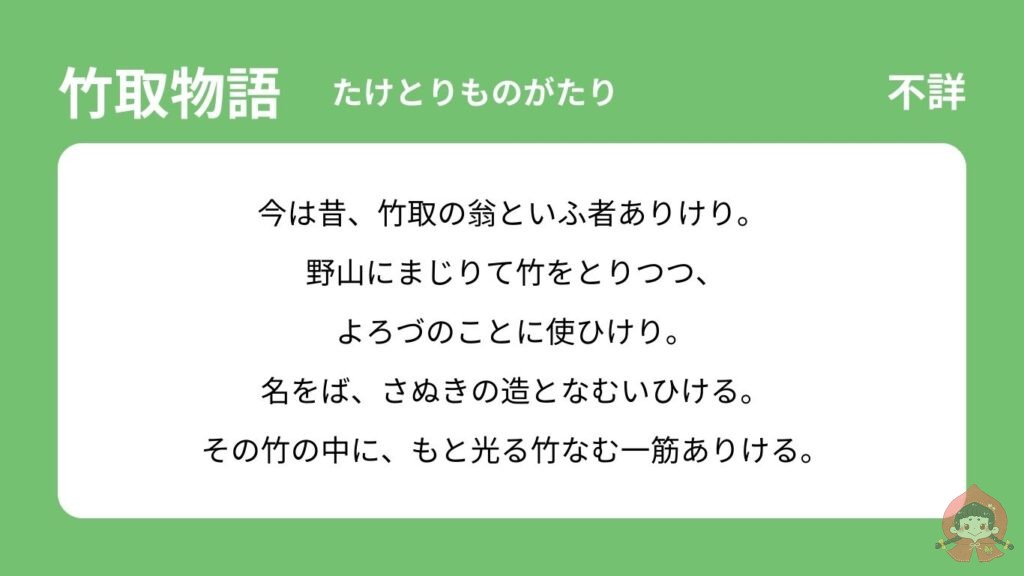
『竹取物語』の冒頭文を解説しました。
リズムよく端的、かつ惹き込まれる冒頭です。
有名な冒頭文なので、細かく意味を覚えておけると便利だと思います。
▼古典のノミチ記事はこちら!