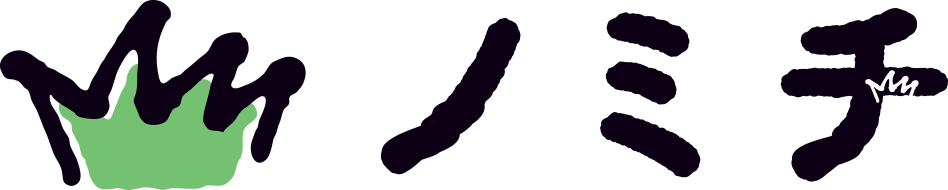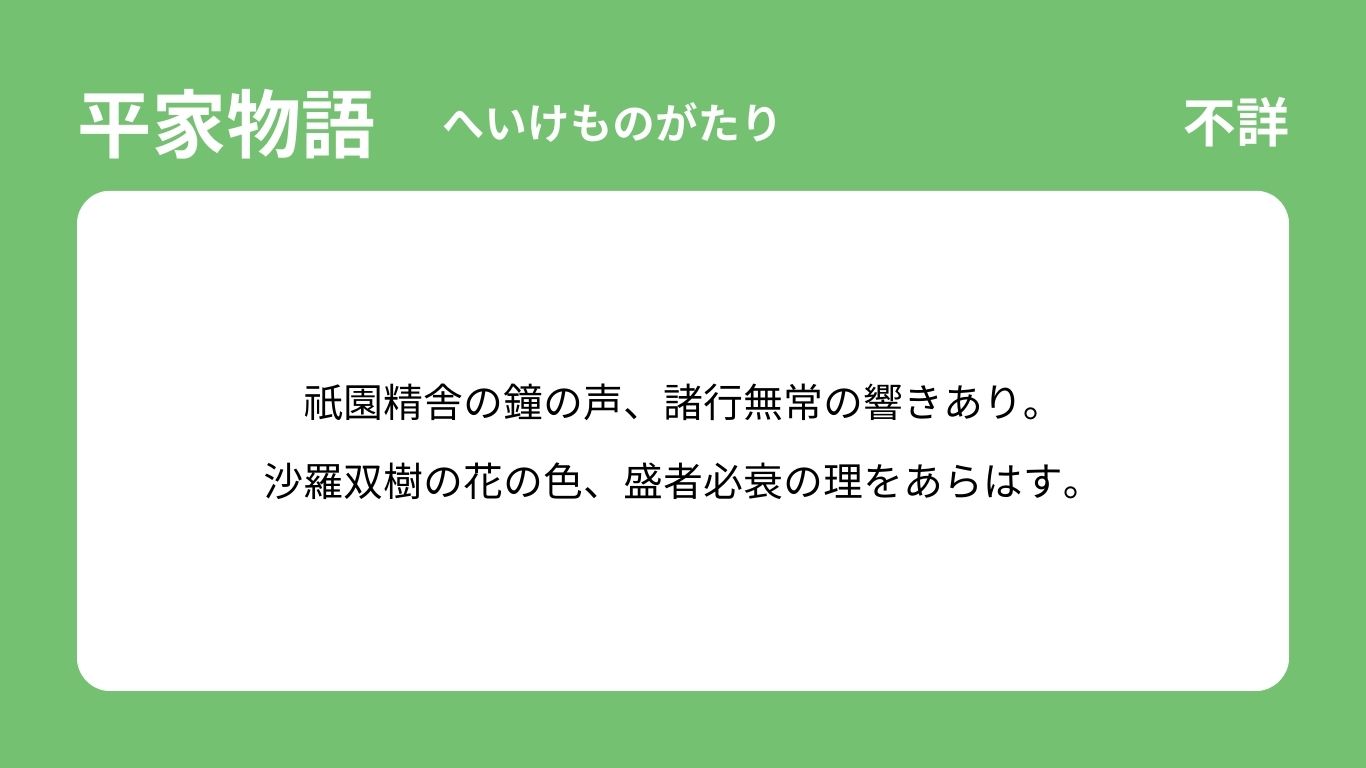一里塚(いちりづか)とは、室町時代や江戸時代に整備された主要な街道沿いに建てられた塚。
確かな地図がなかった当時、一里塚は重要な役割を果たしていました。
一里塚とは何かについて、目的や役割と一緒にご紹介します。
▼街道に便利な用語集はこちら!
一里塚とは?
確かな地図がなかった当時、旅人たちの道標となったのが「一里塚」です。
一里とは、3.927キロ(約4キロ弱)のことだよ!
ただし寺社や非人の居住地は距離に含まれず、難所は概算だったため、「一里」の距離はまちまちだったとか。
一里塚の歴史は古く、平安時代末期に奥州藤原氏が白河の関〜陸奥湾の間に標識を立てたのが最初だといわれています。

江戸時代になると幕府が「五街道」を整備しました。
その街道沿いに、一里ごとに設けられたのが一里塚です。道路の両脇に土が盛られ、その上に榎や松の木が1〜数本植えられました。
今でも松並木が残っていることがありますが、ほとんどは明治期までに荒廃していきました。
一里塚の目的は?
①距離を把握するため
1つ目の目的は距離を把握すること。旅人が歩いている時、一里ごとに標があればどれだけ歩いたか、どこまで歩くかの目安にすることができます。
②休憩場所にするため
2つ目の目的は休憩場所にすること。
並木は木陰にもなるため、旅人が休憩するのにうってつけの場所になるのです。
③運賃を把握するため
3つ目の目的は運賃を把握すること。
馬や駕籠(カゴ)を使って人や荷物を運ぶ際、一里ごとに運賃が定められていました。そのため一里塚は運賃を把握する役割も果たしていたのです。
一里塚のことわざや例え
門松は冥土の旅の一里塚|一休の狂歌
室町時代の一休の狂歌に「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」というものがあります。
人生を旅に例えたとき、年を重ねる度に飾る門松を一里塚に例えています。めでたい門松ではあるけれど、死へ向かっていると考えるとめでたくないともいえますよね。
一里塚とは?まとめ

一里塚とは?をご紹介しました。
たまに街道沿いに見かける「一里塚」の看板や松並木ですが、その役割を知っていると昔の旅人気分が味わえるかもしれませんね。
▼ノミチ用語解説記事
-
 歴史・文化
歴史・文化 本陣とは?江戸時代の宿泊施設の意味と役割を分かりやすく解説
江戸時代、日本全国に広がった宿場町には「本陣(ほんじん)」という特別な宿泊施設がありました。 本陣は一般の宿泊所とは異なり、武士や幕府の役人など、身分の高い人々のために設けられた特別な宿です。 この記事では、江戸時代の交 […] -
 歴史・文化
歴史・文化 【3分で解説】平家物語とは?物語の概要と魅力をわかりやすく解説
「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり…」 平家物語の冒頭に登場するこの有名な一節は、栄光と衰退、そして人生の儚さを象徴する言葉です。 平家物語は、日本の歴史や文学の中で非常に重要な作品であり、源平合戦を中心に、平家一族 […] -
 歴史・文化
歴史・文化 江戸時代の交差点!「追分(おいわけ)」とは?意味と歴史を分かりやすく解説
日本の歴史の中で、江戸時代の街道は重要な役割を果たしました。 その街道の中でも、特に「追分(おいわけ)」と呼ばれる場所は、旅人にとって欠かせない分岐点でした。 この記事では、追分とは何か、なぜ重要だったのか、そしてその歴 […] -
 歴史・文化
歴史・文化 『おくのほそ道』とは?松尾芭蕉の名作と旅の背景をわかりやすく解説
『おくのほそ道』とは、俳人・松尾芭蕉が江戸から東北、北陸を歩いて記した紀行文です。 江戸時代前期の元禄15(1702)年に出版されました。旅で立ち寄った名所の感想とともに、その土地で書いた俳句を掲載しています。 今回はそ […] -
 歴史・文化
歴史・文化 覚えておきたい街道用語20選|宿場や関所の意味をわかりやすく紹介
日本各地を結ぶ街道は人々の生活や文化に欠かせない存在でした。 街道は物流や人の移動、参勤交代といった重要な役割を果たし、現代にもその名残が各地に残っています。今回は、そんな「街道」に関する20の基本用語を初心者にもわかり […] -
 歴史・文化
歴史・文化 「五畿七道(ごきしちどう)」の歴史と役割とは?古代日本の行政区分を探る
日本の歴史において、五畿七道は行政や交通の重要な基盤として機能していました。 五畿七道は、奈良時代に確立された行政区分であり、交通網としても整備されたもので、現在の日本の都道府県のルーツにもつながっています。 本記事では […]