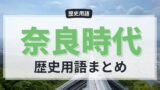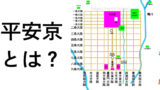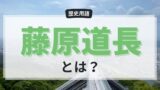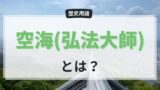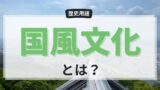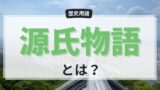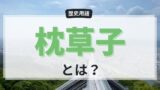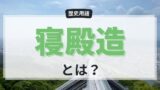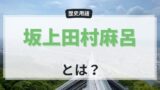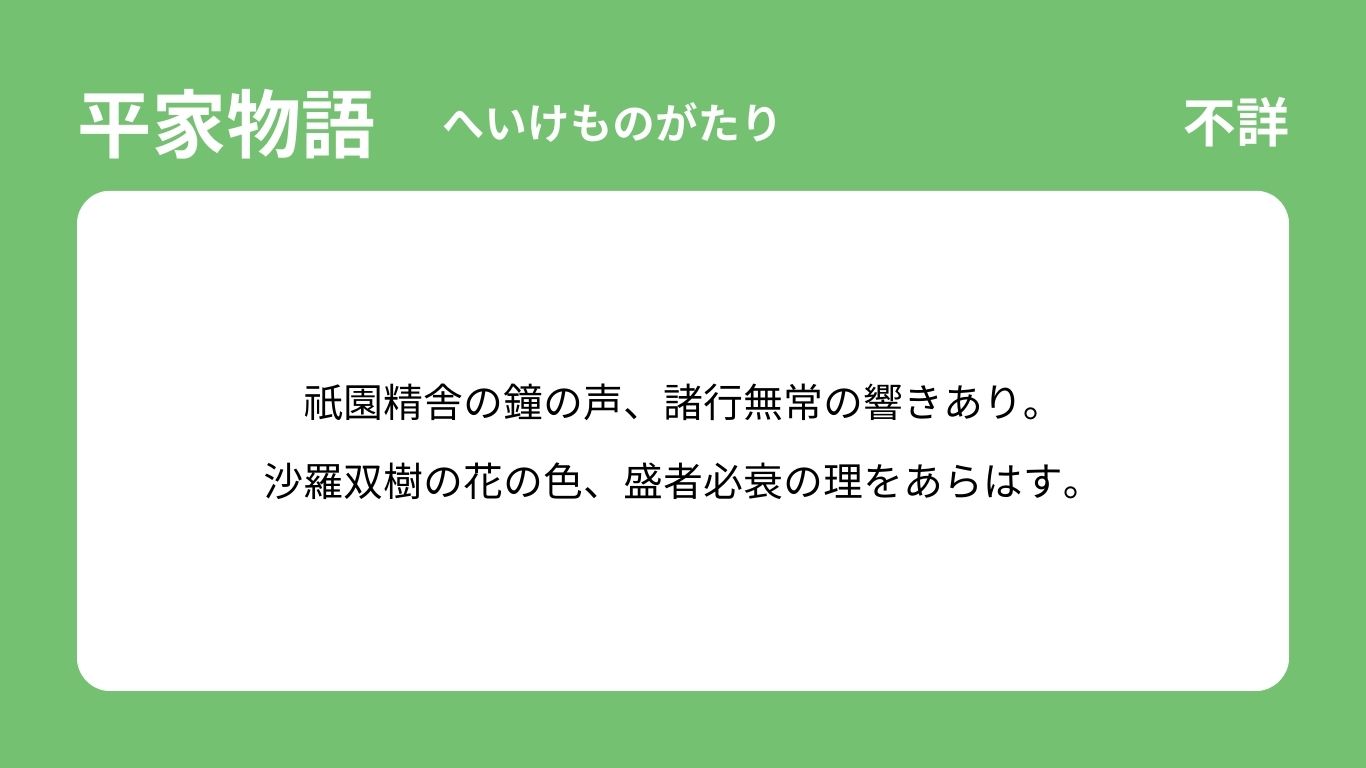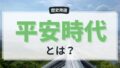平安時代(794年〜1185年)は、日本史における長期の安定期であり、政治・文化・社会のさまざまな変化が起きた時代です。
桓武天皇による平安京遷都をきっかけに、律令制を基盤とした中央集権的政治が行われる一方で、貴族文化や仏教文化が大きく発展しました。さらに、武士の台頭が始まり、後の鎌倉幕府へとつながる時代でもあります。本記事では、平安時代の政治、文化、社会、そして受験で覚えておきたい歴史用語をわかりやすく解説します。
- 平安時代とは?
- 平安時代の歴史用語1 平安京
- 平安時代の歴史用語2 桓武天皇
- 平安時代の歴史用語3 摂関政治
- 平安時代の歴史用語4 藤原道長
- 平安時代の歴史用語5 院政
- 平安時代の歴史用語6 空海(弘法大師)
- 平安時代の歴史用語7 最澄
- 平安時代の歴史用語8 国風文化
- 平安時代の歴史用語9 源氏物語
- 平安時代の歴史用語10 枕草子
- 平安時代の歴史用語11 延暦寺
- 平安時代の歴史用語12 寝殿造
- 平安時代の歴史用語13 坂上田村麻呂
- 平安時代の歴史用語14 荘園
- 平安時代の歴史用語15 延喜式
- 平安時代の歴史用語16 保元の乱
- 平安時代の歴史用語17 平治の乱
- 平安時代の歴史用語18 平清盛
- 平安時代の歴史用語19 源頼朝
- 平安時代の歴史用語20 平家物語
- まとめ|「平安時代」が学べる歴史用語20選!受験にもおすすめ
平安時代とは?
平安時代は、桓武天皇が平安京(現在の京都)に都を移した794年から始まります。
それまでの都である長岡京や藤原京よりも広く、碁盤の目のように整備された都市でした。天皇を中心とする律令国家が形骸化する一方で、貴族が政治の実権を握る摂関政治が発展しました。文化面では国風文化が栄え、『源氏物語』や『枕草子』などの文学が誕生しました。
また、地方では武士が台頭し、荘園制度の拡大も進んでいきました。平安時代は、律令制の完成期であると同時に、日本独自の文化と武士社会の基盤が形成された重要な時代です。
平安時代の歴史用語1 平安京
平安京(へいあんきょう)とは、794年に桓武天皇によって建設された都。
長岡京から遷都され、碁盤の目のように整備された都市計画が特徴です。都の中心には天皇の居住する内裏(だいり)があり、政務の中心として機能しました。都内には貴族の邸宅が立ち並び、文化活動の拠点となりました。また、都の設計は風水や中国の長安をモデルにしており、政治的・文化的な象徴性を兼ね備えています。
平安時代の歴史用語2 桓武天皇
桓武天皇(かんむてんのう)とは、平安時代の始まりを作った天皇。
平安京への遷都を行い、地方の反乱鎮圧や律令制度の再整備を進めました。特に地方行政の安定化に努め、地方豪族や武士を統制するための政策を実施しました。また、文化面でも仏教の保護や寺院建設を支援し、国家の権威を強化しました。
平安時代の歴史用語3 摂関政治
摂関政治(せっかんせいじ)とは、天皇が幼少や政治不在の時に、藤原氏などの貴族が摂政・関白として政治を実質的に運営する制度です。
藤原氏は娘を天皇の后に送り込み、外戚関係を利用して権力を拡大しました。この仕組みにより、藤原氏は数世紀にわたり平安政治の実権を握りました。
平安時代の歴史用語4 藤原道長
藤原道長(ふじわらのみちなが)とは、平安時代中期の摂政・関白で、権勢を極めた貴族。
娘を天皇の后とし、外戚として政治を掌握しました。特に「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」という和歌に象徴されるように、当時の貴族社会で絶対的な権力を持っていました。
平安時代の歴史用語5 院政
院政(いんせい)とは、天皇が退位した後、上皇となって政治を指導する制度。
上皇が院庁を設けて政務を執り、摂関や公家の政治とは別に権力を行使しました。これにより、権力構造が複雑化し、貴族社会と武士社会の力関係にも影響を与えました。
平安時代の歴史用語6 空海(弘法大師)
空海(弘法大師)とは、真言宗(しんごんしゅう)を開いた僧。
密教の教えを日本に広め、東寺や金剛峯寺などの寺院建設を行いました。書道や学問にも優れ、多くの文化的功績を残しています。弘法大師は平安時代の宗教文化に多大な影響を与え、日本文化の形成に寄与しました。
平安時代の歴史用語7 最澄
最澄(さいちょう)とは、天台宗(てんだいしゅう)を開いた僧。
比叡山延暦寺を建立し、仏教教育の基礎を作りました。密教や禅の教えも学び、国家仏教としての地位を確立することで平安時代の宗教文化を発展させました。
平安時代の歴史用語8 国風文化
国風文化(こくふうぶんか)とは、平安時代に栄えた日本独自の文化。
中国文化の影響を受けつつ、日本らしい表現を重視しました。和歌や物語、絵巻、寝殿造などが発展し、貴族社会の生活や美意識を反映しています。特に宮廷を中心に広まり、後世の日本文化に大きな影響を与えました。
平安時代の歴史用語9 源氏物語
源氏物語(げんじものがたり)とは、紫式部による長編物語で、平安貴族の恋愛や宮廷生活を描いた作品。
世界最古級の長編小説ともいわれ、登場人物の心理描写や社会状況を詳細に描写しています。文学史や文化史の学習で欠かせない作品です。
平安時代の歴史用語10 枕草子
枕草子(まくらのそうし)とは、清少納言(せいしょうなごん)による随筆。
宮廷生活の様子や四季折々の風物、人々の機微を記録しており、国風文化を知るうえで重要です。文章の形式や観察眼も評価され、文学史上高く評価されています。
平安時代の歴史用語11 延暦寺
延暦寺(えんりゃくじ)は、最澄が創建した天台宗の総本山。
比叡山にあり、仏教教育や修行の中心となりました。国家仏教としての役割も持ち、後の日本仏教や僧兵の成立に影響を与えました。
平安時代の歴史用語12 寝殿造
寝殿造(しんでんづくり)は、貴族住宅の建築様式。
庭園や回廊を取り入れた優雅な造りで、貴族の生活様式や権威を反映しています。寝殿造の設計は平安時代の美意識を理解する上で重要です。
平安時代の歴史用語13 坂上田村麻呂
坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)は、平安時代初期に活躍した武人。
日本史上初めて「征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)」に任じられた人物です。
東北地方に住んでいた蝦夷(えみし)を討伐・服属させる役割を担い、平安政権の拡大に大きく貢献しました。
平安時代の歴史用語14 荘園
荘園(しょうえん)は、貴族や寺社が所有する私有地で、租税の免除を受けることができました。
中央政府の権力低下とともに拡大し、平安後期の財政や地方支配に大きな影響を与えました。
平安時代の歴史用語15 延喜式
延喜式(えんぎしき)とは、醍醐天皇の時代に編纂された律令制の施行細則集。
律令制度の具体的運用を定め、中央・地方行政の基準となりました。受験では律令制度関連の用語として重要です。
平安時代の歴史用語16 保元の乱
保元の乱(ほうげんのらん)は、1156年に発生した源氏と平氏による内乱。
院政下で天皇と上皇の権力争いが激化し、源氏と平氏が対立するきっかけとなりました。平安末期の政治混乱を象徴する事件です。
平安時代の歴史用語17 平治の乱
平治の乱(へいじのらん)は、1159年に発生した源氏と平次による内乱。
源氏と平氏の対立が激化し、平清盛が権力を掌握する契機となった戦いです。武士の政治的役割が顕著になった重要な事件です。
平安時代の歴史用語18 平清盛
平清盛(たいらのきよもり)は、武士として初めて国家の政治の頂点に立った武士。
太政大臣に就任し、平安末期の武士政治の先駆けとなりました。
平安時代の歴史用語19 源頼朝
源頼朝(みなもとのよりとも)は、鎌倉幕府を開いた武士。
平安時代末期の源平合戦を経て、武士政権の礎を築きました。武士の政治的役割と地方支配の重要性を象徴する人物です。
平安時代の歴史用語20 平家物語
平家物語(へいけものがたり)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて成立した軍記物語。
平氏一族の栄枯盛衰を描き、源平合戦の経過や武士の生き様を伝えています。琵琶法師によって語り継がれ、武士道や歴史認識の形成にも大きな影響を与えました。受験では武士の台頭や院政期の政治動向を理解するうえで欠かせない作品です。
まとめ|「平安時代」が学べる歴史用語20選!受験にもおすすめ

平安時代は、桓武天皇の平安京遷都を契機に、貴族政治、国風文化、仏教文化、武士の台頭など、多様な変化が起きた時代です。
律令制度の形骸化や摂関政治、荘園の拡大は社会構造を複雑化させ、武士政権への移行を促しました。また、『源氏物語』や『枕草子』などの文学作品、寝殿造や絵巻などの美術作品は、日本独自の文化を理解するうえで欠かせません。
受験においても、平安時代の政治・文化・社会の流れを押さえることは非常に重要です。歴史用語20選を学ぶことで、平安時代の全体像を体系的に理解でき、古代から中世への流れも把握できます。
▼歴史用語の記事はこちら!