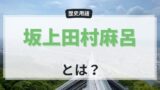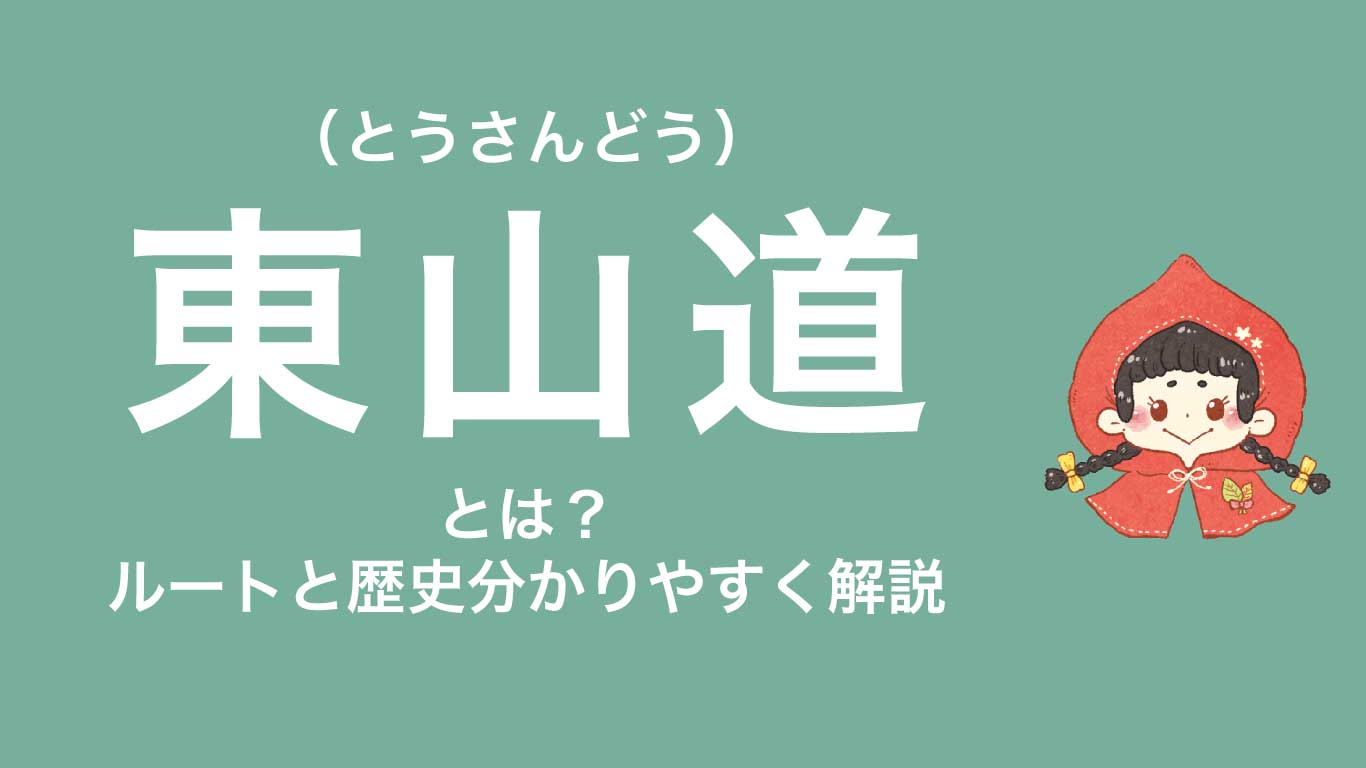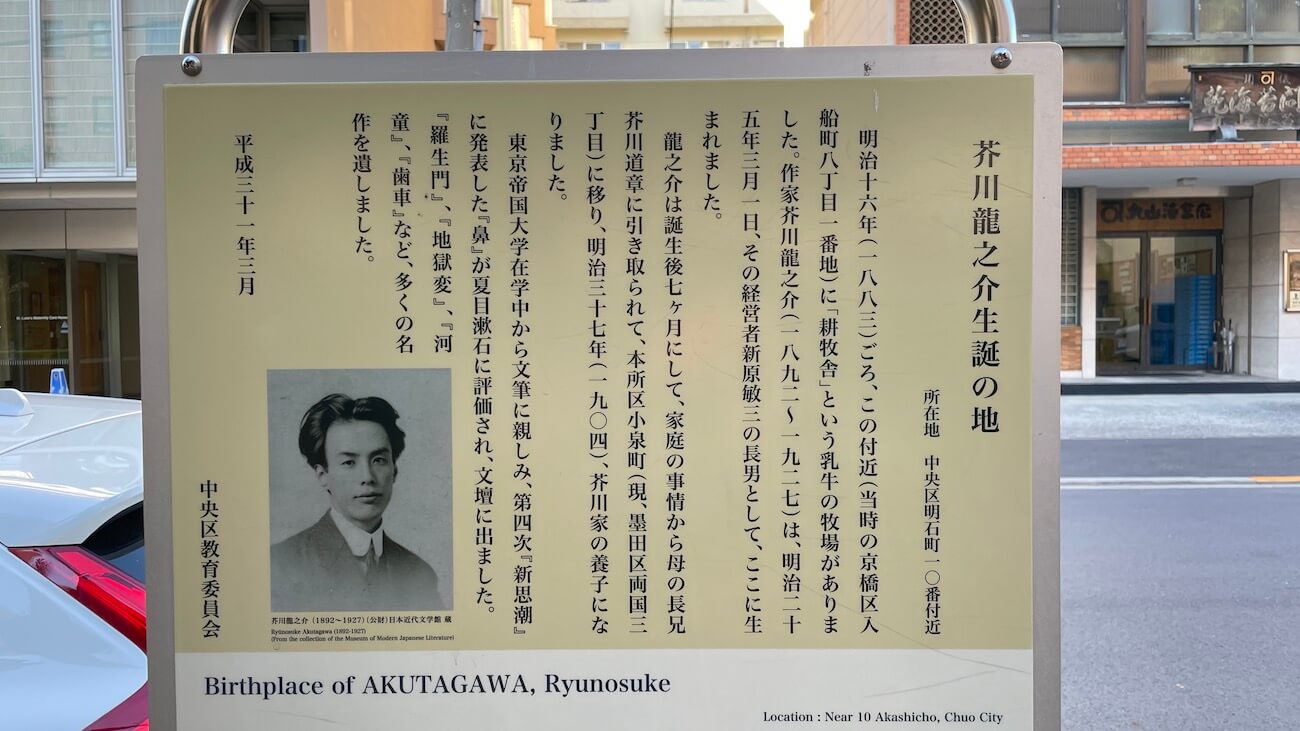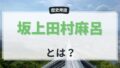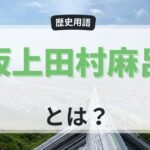坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)は、平安時代初期に活躍した征夷大将軍であり、蝦夷(えみし)征討の指揮を執った人物です。
彼の遠征において重要な役割を果たしたのが、古代の幹線道路である「東山道(とうさんどう)」でした。この記事では、坂上田村麻呂の人物像や蝦夷との戦い、そして彼が歩んだとされるルートや立ち寄った史跡について分かりやすく解説します。受験勉強や歴史探訪にも役立つ内容です。
坂上田村麻呂とは?
坂上田村麻呂(758〜811)は、奈良時代末期から平安時代初期にかけて朝廷に仕えた武人です。桓武天皇の信任を受け、日本で初めて「征夷大将軍」に任命されたことで知られています。
田村麻呂の役割は、東北地方に住む蝦夷の反乱を鎮め、律令国家の支配を拡大することでした。彼は武勇に優れるだけでなく、敵に対しても寛大な態度をとった人物とされ、後世には「武人の鑑」とも称されています。
蝦夷とアテルイ
東北地方の蝦夷は、大和朝廷の支配に抵抗を続けました。その中でも有名なのが、蝦夷のリーダー「アテルイ」と「モレ」です。
田村麻呂は802年、奥羽地方で大規模な戦いを行い、最終的にアテルイとモレは降伏します。田村麻呂は二人の助命を嘆願しましたが、朝廷の意向により処刑されてしまいました。このエピソードは、彼がただの武将ではなく、敵の命を尊重する人格者であったことを示すものとして語り継がれています。
坂上田村麻呂の遠征ルートは東山道
田村麻呂の活動範囲を示す「明確なルート」は現存しませんが、文献や考古学的調査から、主に東山道を拠点とする遠征ルートが想定されています。
東山道とは?

東山道は、律令制下の「七道」の一つで、畿内から美濃・信濃を経由して、上野・下野、さらに陸奥へと通じる幹線道路です。古代の軍事・交通の要衝であり、朝廷が東北経営を進める上で不可欠なルートでした。
田村麻呂は、この東山道を進軍路とし、奥羽地方での戦いや城柵(じょうさく)建設を行ったと考えられています。
東海道・奥羽山脈越えの道
また、場合によっては東海道を経て北上するルートや、奥羽山脈を越える山道も利用したと推測されます。これにより、京都から東北各地へと軍勢を送り込むことが可能になりました。
坂上田村麻呂が立ち寄った史跡
田村麻呂の遠征に関連する史跡は、東北各地に残されています。特に重要なのは以下の3つです。
多賀城跡(宮城県多賀城市)
多賀城は724年に築かれた陸奥国の国府・鎮守府で、東北経営の拠点でした。田村麻呂もここを拠点として蝦夷征討を行ったと考えられています。現在は国の特別史跡に指定されており、発掘調査により当時の建物跡が確認されています。
胆沢城(岩手県奥州市)
802年、田村麻呂は胆沢城(いさわじょう)を築き、東北支配の前進基地としました。ここは北上川流域を押さえる重要拠点であり、蝦夷征討後の統治を支える役割を果たしました。胆沢城跡には現在も碑や遺構が残り、歴史ファンが訪れるスポットとなっています。
志波城(岩手県盛岡市)
胆沢城の北方に位置する志波城(しわじょう)は、803年に築かれた城柵で、当時としては最大規模を誇りました。東北地方のさらなる支配を進めるための拠点であり、田村麻呂の戦略的な活動を示す重要な遺跡です。
まとめ|坂上田村麻呂の征夷ルート「東山道」遠征の道筋と伝承の地をたどる

坂上田村麻呂の遠征ルートは、明確には特定されていませんが、東山道を中心としたルートであることは確かです。彼は多賀城・胆沢城・志波城といった拠点を築きながら、蝦夷征討を進め、最終的に朝廷の支配を東北へ拡大しました。
田村麻呂の足跡をたどることで、単なる戦の記録ではなく、古代日本の国家形成の過程や、地域ごとの歴史の深みを感じることができます。現代の私たちが訪れる史跡も、かつての「ルート」の一部を物語っているのです。
▼歴史上の偉人ノミチ記事はこちら