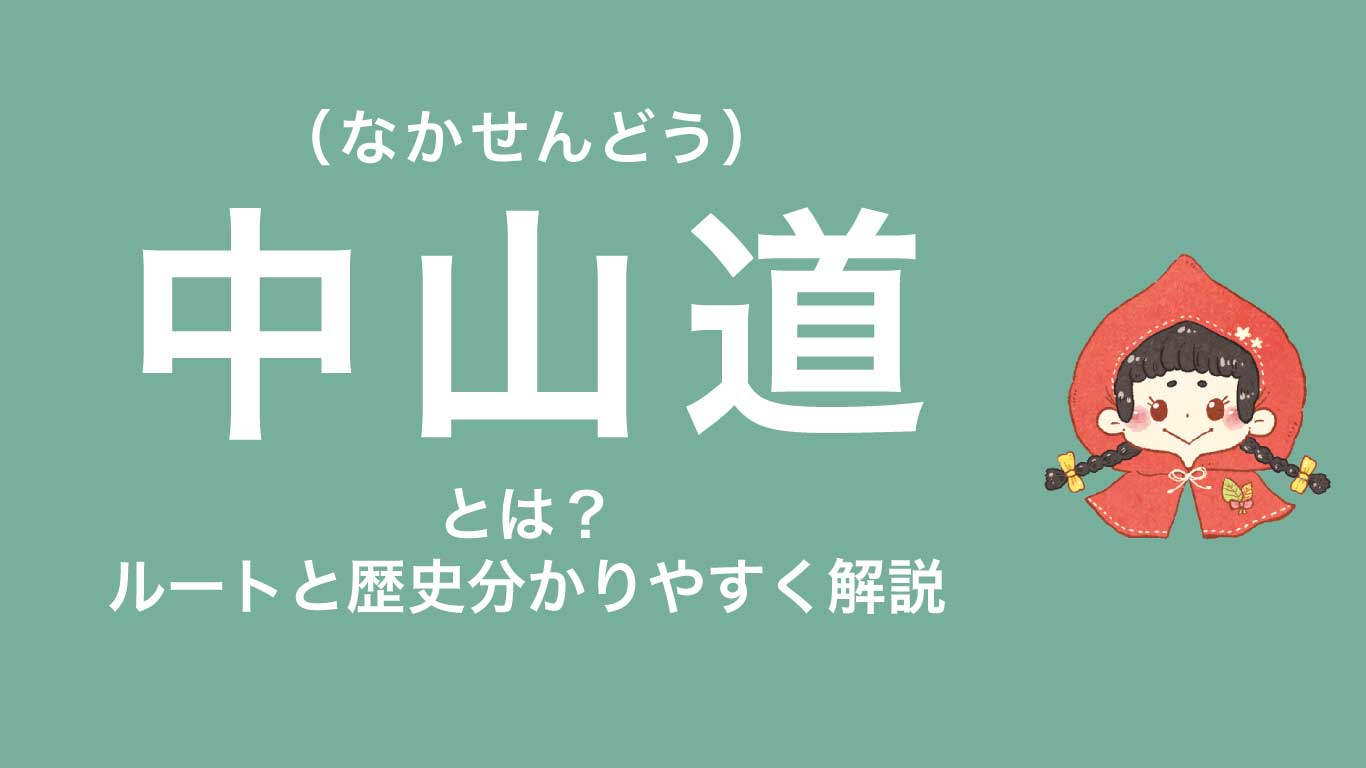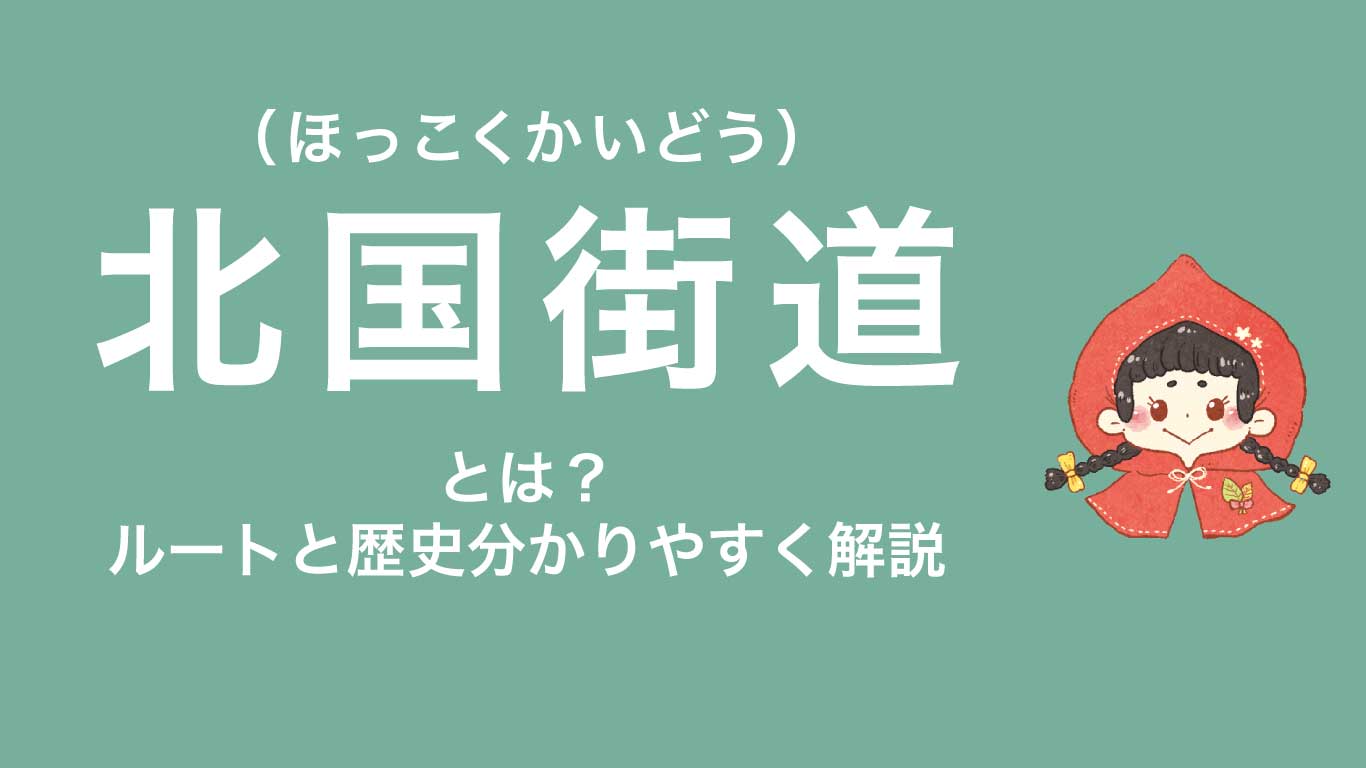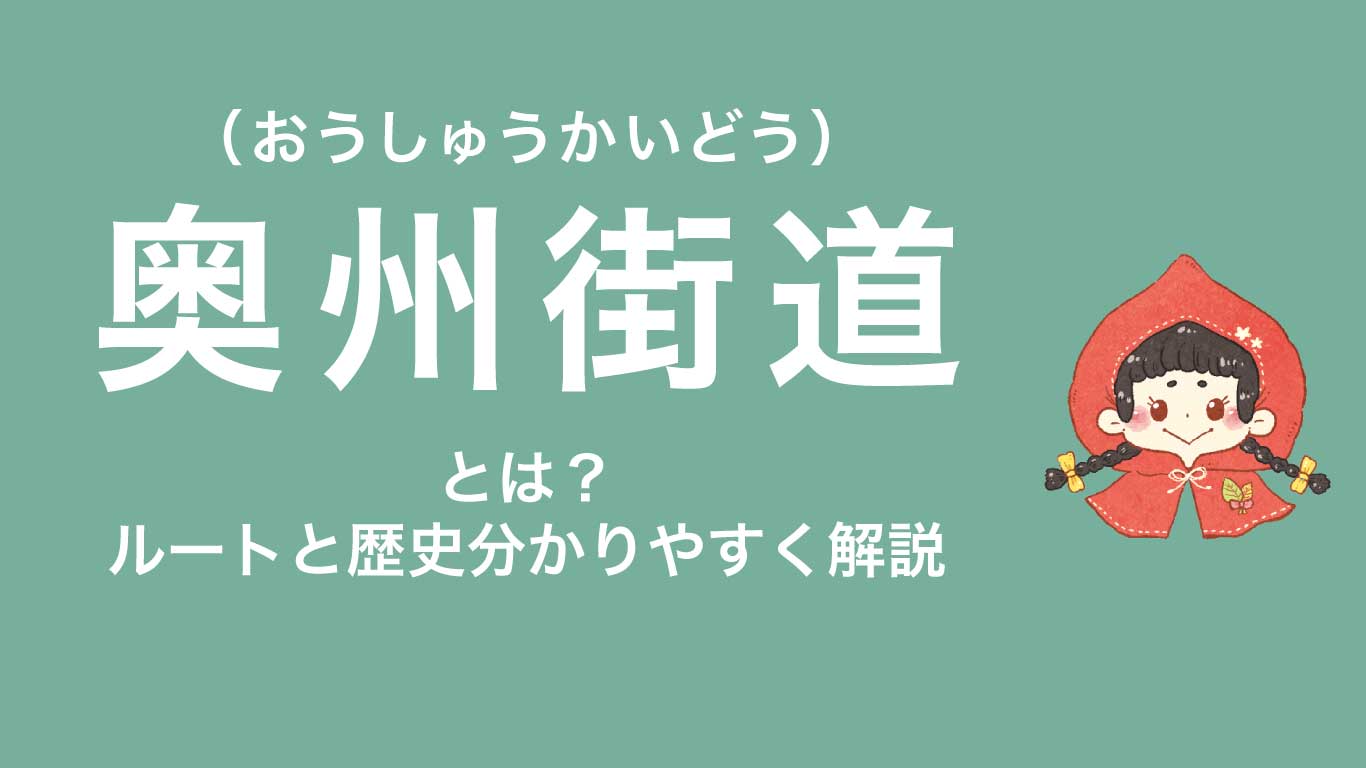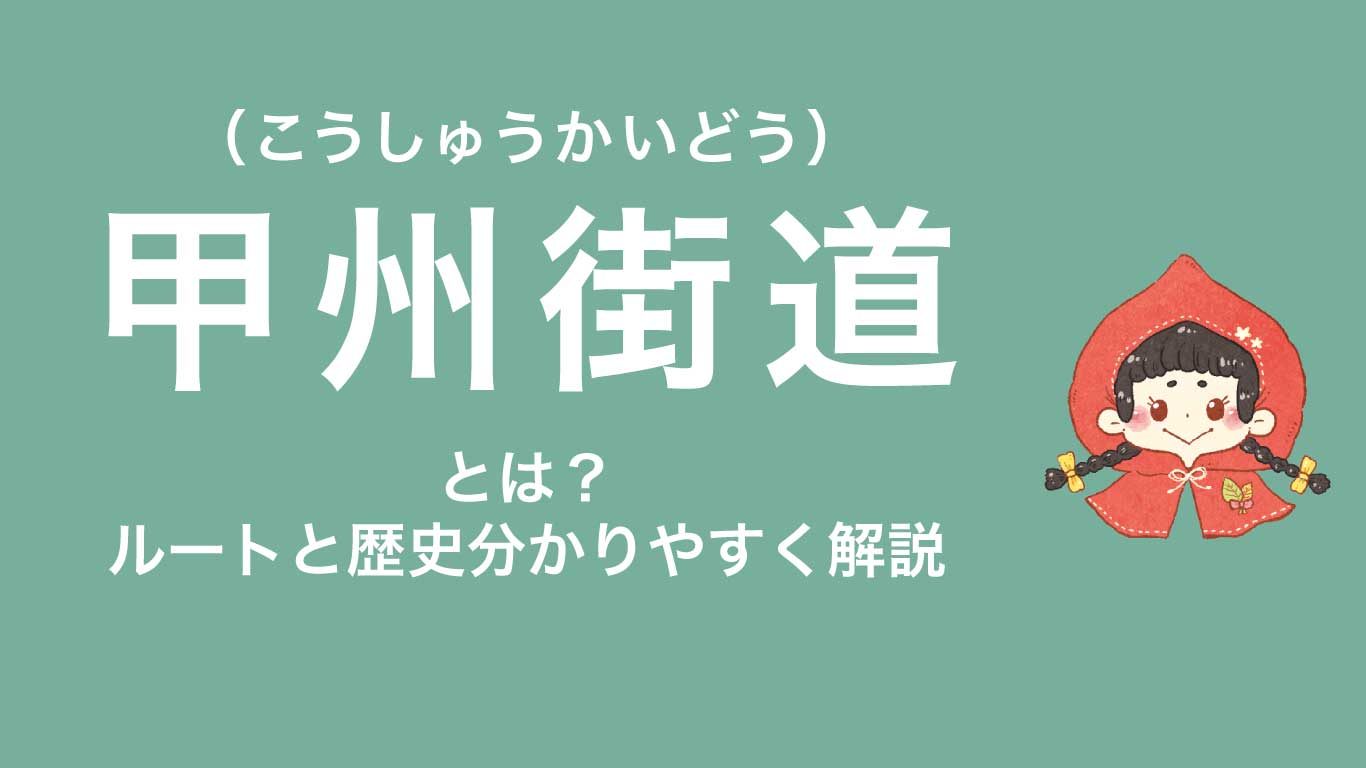江戸時代を旅したり、宿場町で暮らした庶民にとって、最も身近でありながら権威を感じさせる存在が「高札場(こうさつば)」でした。現代の私たちが街で掲示板や看板を見るように、当時の人々もまずは高札場を通して「お上の意向」を知ったのです。
では、高札場とは具体的にどのような施設だったのでしょうか。どんな内容が掲げられていたのか、どこに設置され、人々にどのように受け止められていたのか。そして今なお残る高札場の史跡についても紹介していきます。
高札場とは?

高札場とは、幕府や藩が発する 法令・禁令を記した木札(高札)を掲げる場所 のことです。高い位置に掲げられるため「高札」と呼ばれました。
江戸幕府は庶民の生活を細かく統制する仕組みを整え、全国にその掟を周知する必要がありました。印刷物や新聞がまだ普及していなかった時代において、庶民に確実に情報を伝える手段が「高札」だったのです。
現代でたとえるなら、役所の公告掲示板や、街の大きな看板、あるいは政府の公式ウェブサイトのような存在といえるでしょう。
高札に書かれていた内容

高札に掲げられる内容は実に多岐にわたります。具体的には次のようなものが代表的です。
- 禁酒・博打禁止:庶民の風紀を守るため、酒宴や賭博に関する厳しい取り締まりがあった。
- キリシタン禁止令:江戸幕府が最も警戒していたのがキリスト教の布教。踏み絵や禁教令の周知は、高札を通じて徹底された。
- 年貢や通行の取り決め:村ごとに課せられる年貢の納入法、あるいは街道を通る際の規則や関所の取り締まり。
- 犯罪者に関するお触れ:盗賊や脱獄人の手配、捕らえた場合の報奨金なども掲げられた。
高札は単なる「注意事項」ではなく、場合によっては人々の生活や信仰に大きく影響するものでもありました。特にキリシタン禁制の札は、江戸から幕末に至るまで長期間掲示され続け、日本社会の大きな圧力となったのです。
高札場の設置場所

では、高札場はどこに置かれたのでしょうか。設置場所には一定のルールがありました。
- 宿場町:本陣や問屋場の近く、旅人や住民が必ず目にする交通の要所
- 城下町:城下の入口や主要な辻、橋のたもとなど、人が集まりやすい場所
- 農村部:村の中心や神社の境内、村人が集会を開く場所
例えば東海道や中山道といった五街道沿いでは、各宿場に必ず高札場が設けられました。旅人は宿場に入るとまず高札場を目にし、その土地の掟を知ることができたのです。
庶民と高札場の関係
当時の庶民の多くは読み書きができませんでした。寺子屋教育が普及するのは江戸時代後期に入ってからであり、17世紀〜18世紀前半にかけては「読み手」と「聞き手」が分かれていました。
高札場の前では、文字を読める者が音読し、それを周囲の人々が耳で聞いて理解しました。この「読み聞かせ文化」によって、お触れの内容は村や町全体に行き渡りました。さらに、それを家族や隣人へと口伝えすることで、庶民の間に広く浸透していったのです。
高札場は「情報を得る場」であると同時に、人々の社交の場でもありました。お触れの内容をきっかけに世間話が広がり、時には権力への不満や愚痴が飛び交うこともあったでしょう。
高札の形式と特徴
高札そのものは、縦長の木札に墨書きで文字が書かれ、黒塗りの縁取りが施されるのが一般的でした。上部には幕府や藩の紋が記されることもあり、「誰が出した命令なのか」を明確に示しました。
また、高札場には複数の札が掲げられることもありました。全国共通の「五枚札」と呼ばれる高札(禁酒、博打禁止、放火禁止、徒党禁止、キリシタン禁制など)は代表的なもので、どの宿場でも目にすることができたのです。
現代に残る高札場
今日でも各地で高札場を目にすることができます。復元や保存が進み、観光地のシンボルとして親しまれています。
- 奈良井宿(長野県):中山道の宿場町に復元された高札場があり、当時の街道文化を学べる。
- 草津宿(滋賀県):東海道と中山道の分岐点に位置し、多くの旅人が必ず目にした要所。復元施設が観光客に人気。
- 会津若松(福島県):鶴ヶ城周辺に史跡として保存され、城下町の雰囲気を伝える。
- 江戸東京博物館(東京都):館内展示として復元された高札場を見ることができ、江戸の町並みを体感可能。
実際に高札場の前に立ってみると、江戸時代の人々が札を見上げて「今日はどんなお触れが出たのか」と話し合っていた情景が目に浮かびます。
まとめ|高札場(こうさつば)とは?江戸時代の“お触れ掲示板”をわかりやすく解説
高札場は、江戸時代における“公共掲示板”であり、庶民と権力をつなぐ最前線でした。
- 幕府や藩が定めた法令や禁令を周知するために全国に設置
- 宿場町や城下町、村落など人目につく場所に置かれた
- 読み書きできない庶民には口伝えで伝わり、情報共有の場として機能
- 現代にも復元や保存された高札場が残り、街道文化を伝えている
江戸時代の人々が毎日の暮らしの中で必ず目にした高札場。そこには「お上の掟を守らなければならない」という緊張感と同時に、人々の生活の息づかいが凝縮されていました。
街道を歩くときに高札場を見つけたら、ぜひ立ち止まって「ここでどんなお触れが掲げられていたのか」「どんな人々が立ち寄り話し合っていたのか」と想像してみてください。それだけで、数百年前の江戸時代が、ぐっと身近に感じられるはずです。
▼街道用語のノミチ記事はこちら