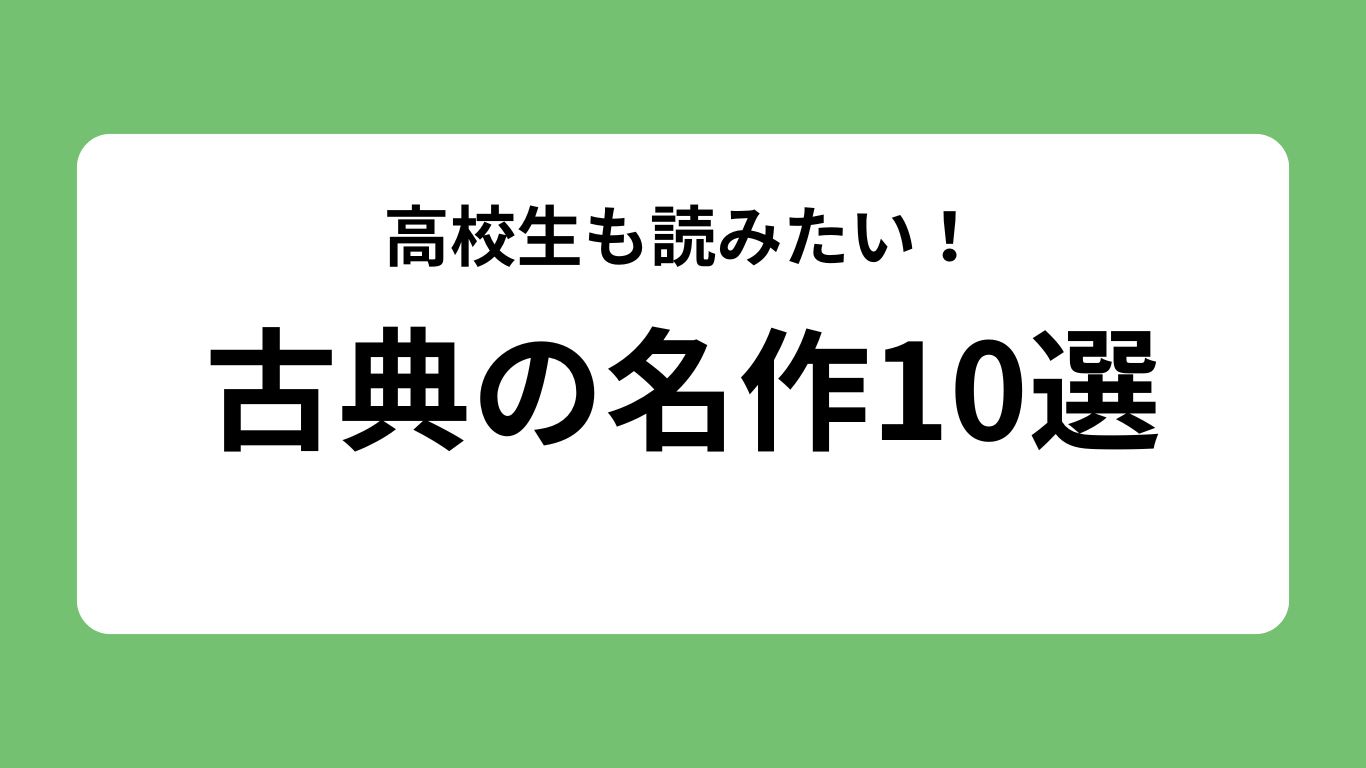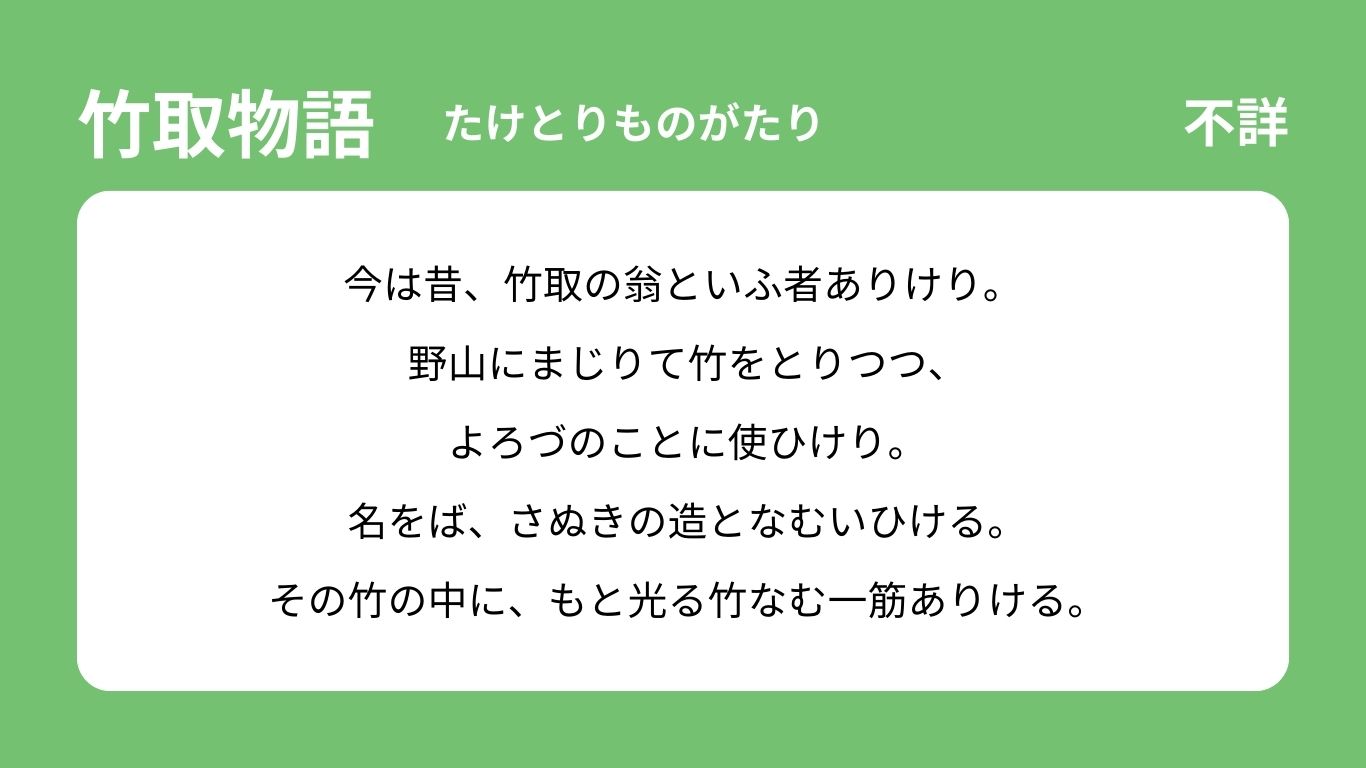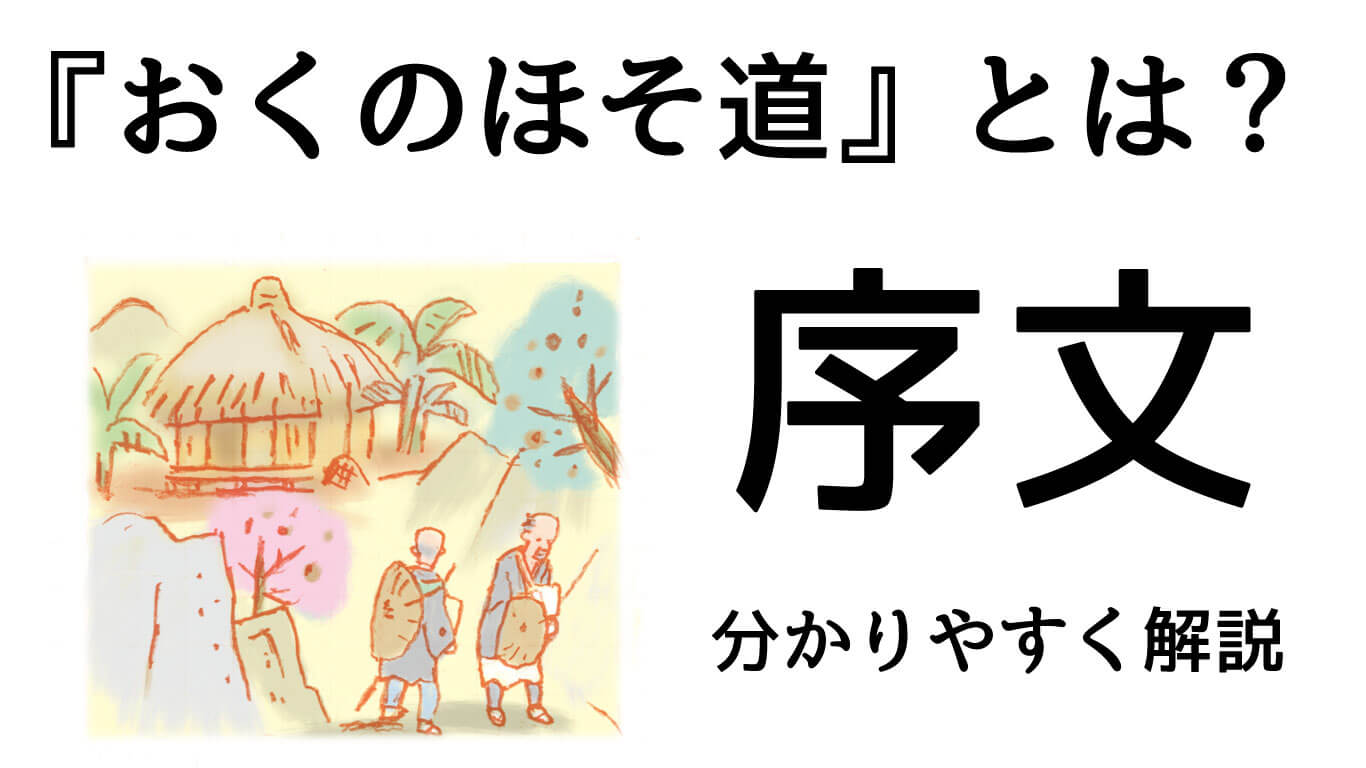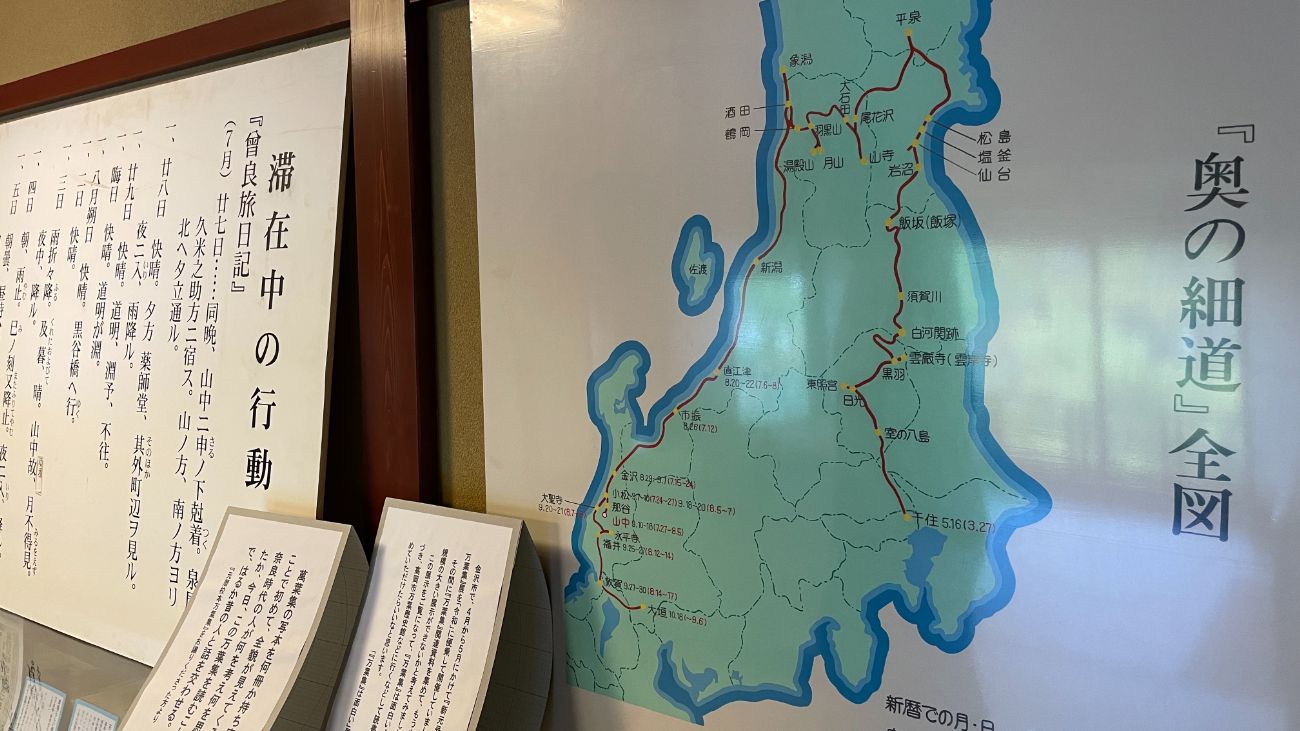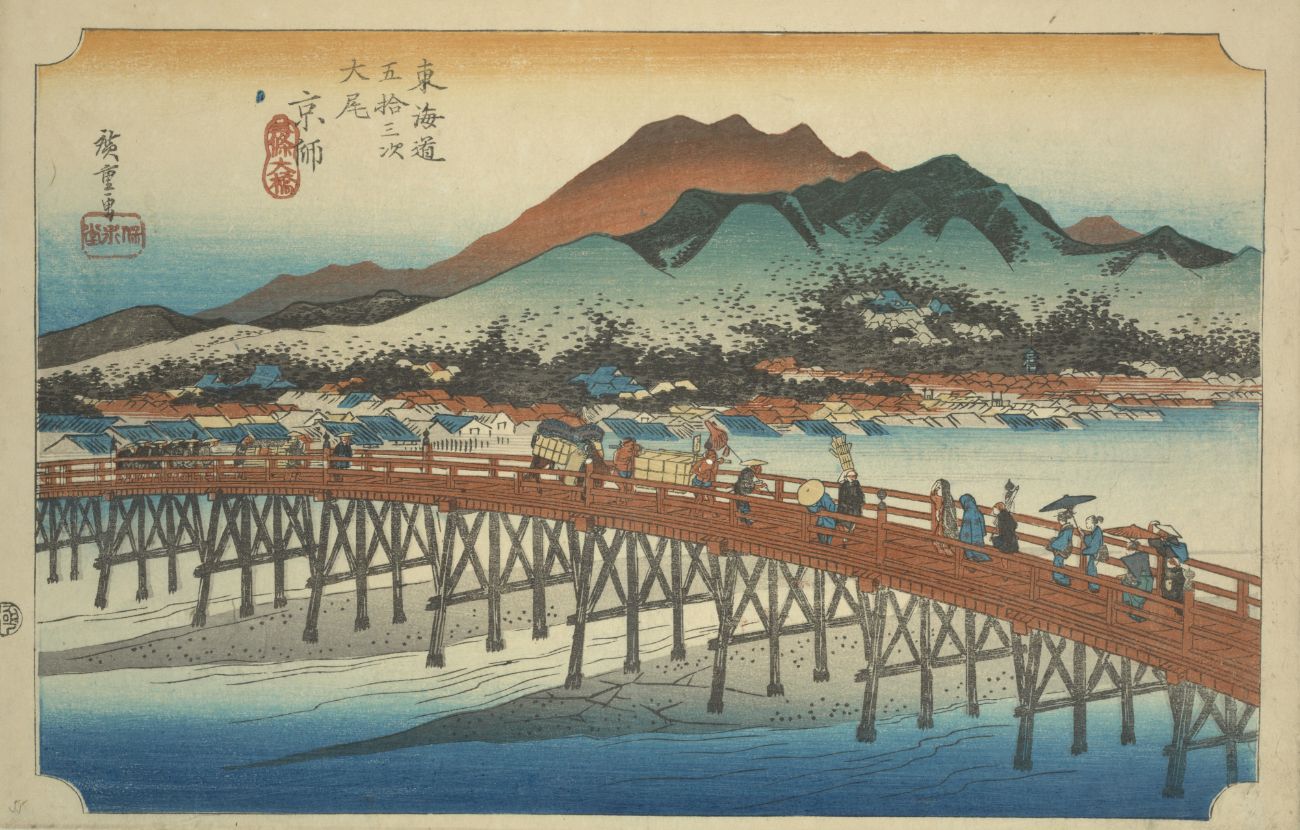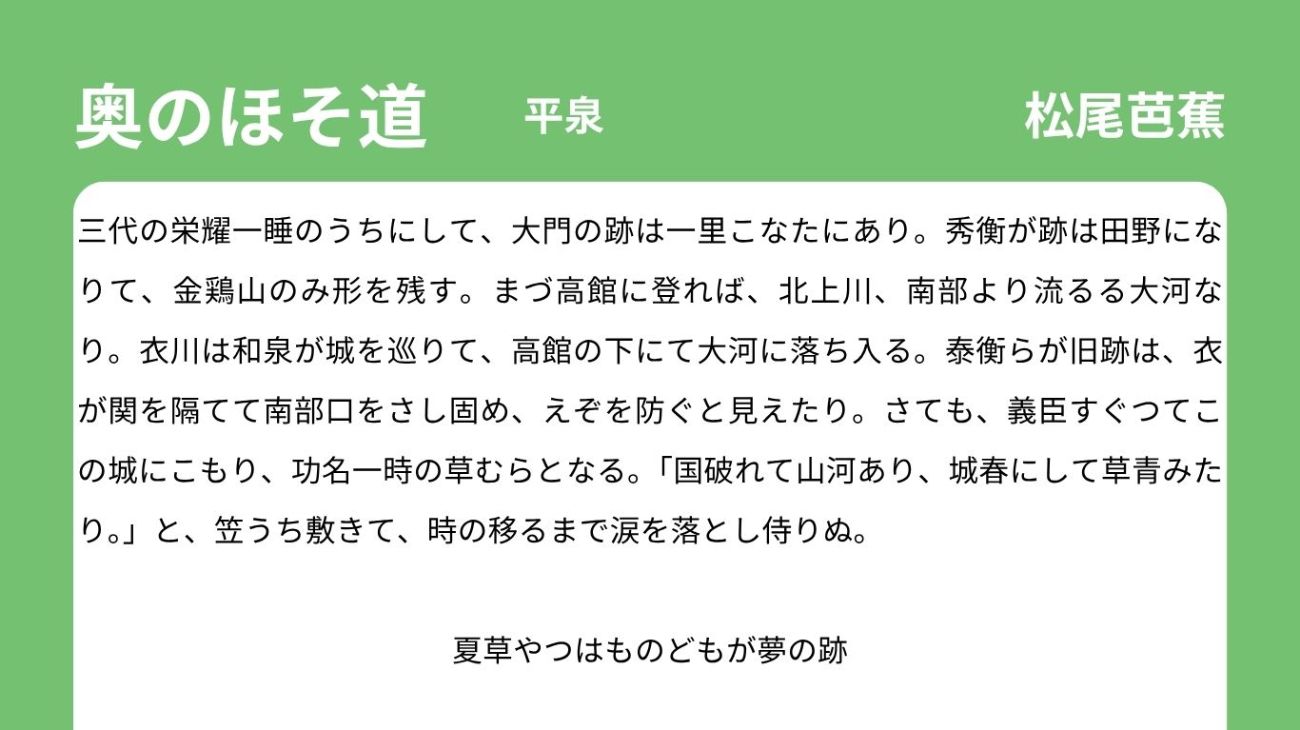『竹取物語』とは、平安時代前期に成立した日本最古級の物語。
「日本最古のSF小説」とも呼ばれ、わたしも中学生の時に教科書で読んで以来大好きな作品です。
現在では「かぐや姫」の話として広く知られています。作者や成立年は不詳ですが、およそ10世紀前半(貞観〜延喜年間:859–923年頃)に、仮名を使える上流階級の知識人によって創作されたと推測されています。
この記事では、「竹取物語とは」何かを初心者向けに解説し、あらすじ・登場人物・背景・魅力を詳しく紹介します。
▼読むべき古典の名作はこちら!
竹取物語とは?平安時代初期・作者不明の物語文学
『竹取物語』は、平安時代の初め頃、10世紀の前半に成立したと考えられている日本最古の物語文学です。
作者は残念ながらわかっていませんが、当時の貴族や知識人の間で広まったと言われています。特徴は、漢字ではなく「仮名(かな)」を使って書かれたことで、これが女性や庶民にも読める文学の普及を促した大きな一歩となりました。
この物語は、現代に伝わる昔話「かぐや姫の物語」の原典ともいえる作品で、神秘的で幻想的な世界観と人間の心の機微を描いた点が多くの人を魅了し続けています。
成立時期・作者
成立は10世紀前半とされ、作者は不明。貴族階層かつ仮名や和歌の知識に長けた知識人による作品と推定されます。
作品の意義
日本に現存する最古の物語文学のひとつで、『源氏物語』に「物語の出で来はじめの祖」と記されるなど、日本文学の原点とも位置づけられています。
▼竹取物語の冒頭文とあらすじはこちらで詳しく解説しています
竹取物語のあらすじ(全体の流れ)
光る竹の中から現れたかぐや姫
物語は、竹取の翁(おきな)が山で光り輝く竹を見つけ、その中から小さな女の子を発見するところから始まります。その子を「かぐや姫」と名付け、大切に育てるのです。かぐや姫は成長するにつれ、その美しさと不思議な魅力で、村中の人々を驚かせる存在になりました。
五人の貴公子からの難題
かぐや姫の美しさは遠くの貴族たちの耳にも届き、多くの求婚者が現れます。しかし彼女は、ただ「はい」とは言いません。五人の求婚者にそれぞれ難題を出します。例えば、燃えない石の鉢や、蓬莱山の玉の枝、火鼠の皮衣など、どれも現実的には到底手に入らない宝物ばかり。彼らは皆、失敗に終わり、それが昔話の中の有名な伝説やことわざの元にもなっているのです。
天皇の求婚と別れ
さらに天皇までもがかぐや姫に求婚しますが、かぐや姫はそれを断り続けます。やがてかぐや姫は自分が月の世界の住人であることを告げ、迎えの使者とともに月へ帰ってしまうのです。残された翁と村人たちは深い悲しみに包まれます。
竹取物語の登場人物一覧
| 人物名 | 説明 |
|---|---|
| 竹取の翁(さぬきの造) | 竹を取り生活し、かぐや姫を育てた老人 |
| 竹取の嫗(おうな) | 翁の妻で、かぐや姫を共に育てる |
| かぐや姫 | 光る竹から現れた美しく才能ある女性。月の都の出身 |
| 五人の貴公子 | 石作皇子・車持皇子・阿倍御主人・大伴御行・石上麻呂(それぞれ難題失敗) |
| 帝(天皇) | 直接求婚するが拒まれる |
| 天人・迎え | かぐや姫を月へ帰す役割を担う |
竹取物語の時代背景とテーマ
当時の日本は、貴族文化が栄え、漢字と仮名の両方が使われるようになった時代です。仮名が広まったことで、物語や和歌が庶民にも伝わるようになりました。
『竹取物語』は、現実と異界が交差する幻想的な世界観が魅力です。かぐや姫が「月の世界の住人」という設定は、当時の人々の宇宙観や死生観を反映しています。また、求婚者に課す難題は、真の価値や志を問うメッセージとして受け取ることもできます。
竹取物語の魅力・読みどころ
- 文学的完成度
複数の伝承・説話を統合し、新たな世界観として再構成した「物語」の誕生として評価されます。 - 語源・故事の宝庫
「はぢを捨てる」「あへなし」「かひなし」など、日常語の語源にもなった逸話の宝庫です。 - 現代への普遍性
美・愛・別れ・運命といった普遍的テーマを含み、現代にも深い共感を呼びます。
竹取物語「かぐや姫」の現代への影響・派生文化
『竹取物語』は、日本の文化や芸術に多大な影響を与えています。
映画やアニメ、小説の題材としても頻繁に取り上げられており、「かぐや姫」は国民的なキャラクターとなっています。また、富士山が不死の薬を焼く場所であるという伝説はこの物語が起源とも言われています。
竹取物語のまとめ
『竹取物語』はただの昔話ではなく、日本文学の原点であり、多くの物語の源流となった作品です。
光る竹から現れたかぐや姫が残した数々の謎や美しい言葉は、私たちに時代を超えたメッセージを届けています。
ぜひ他の古典作品もあわせて読み、日本の豊かな文化に触れてみてくださいね。
▼古典文学のノミチ記事はこちら