 旅行・体験
旅行・体験 山形城(霞城公園)とは?歴史・見どころ・アクセスをわかりやすく解説|日本100名城
山形県山形市にある山形城(霞城公園)は、最上氏の本拠として栄えた東北屈指の名城。日本100名城にも選ばれ、近年は城門・土塀の復元が進み、当時の姿を体感できる貴重な城跡として注目を集めています。春には桜が美しく、駅から徒歩圏内というアクセスの...
 旅行・体験
旅行・体験  歴史の人物・偉人
歴史の人物・偉人  旅行・体験
旅行・体験 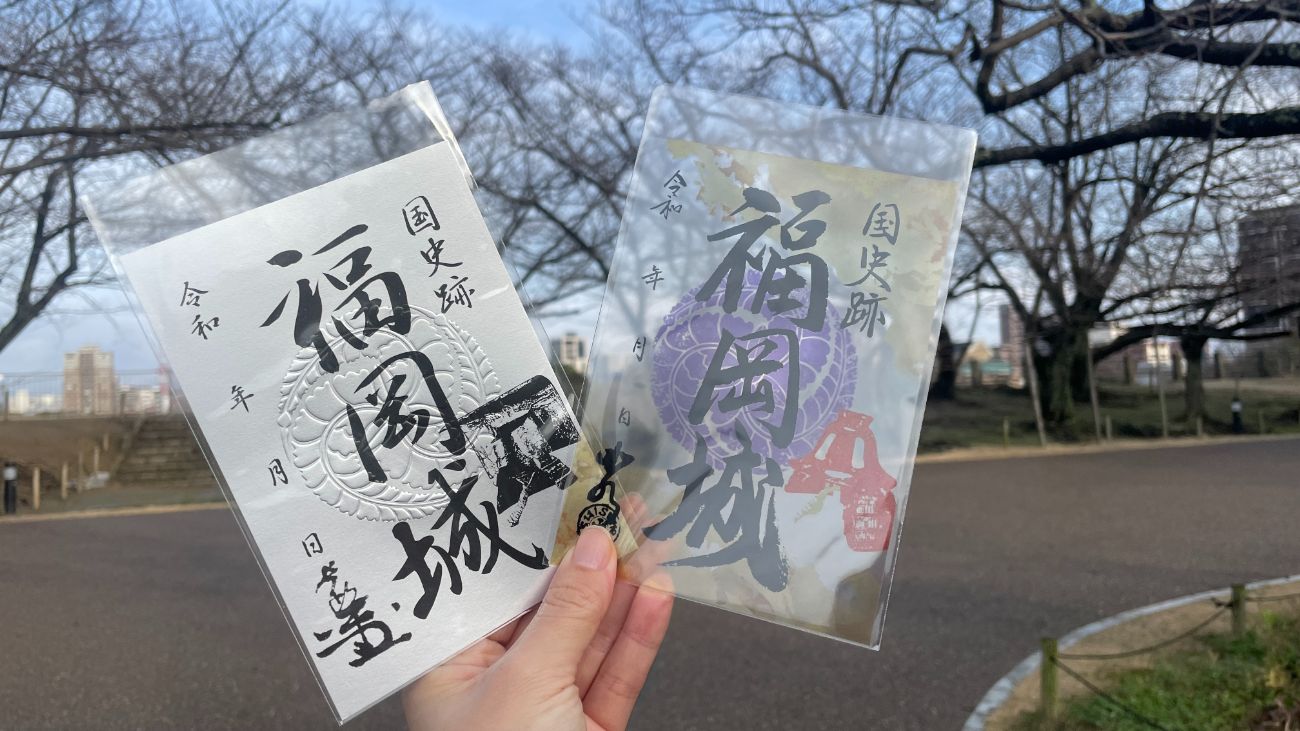 旅行・体験
旅行・体験  城跡・山城
城跡・山城  旅行・体験
旅行・体験  城跡・山城
城跡・山城  旅行・体験
旅行・体験 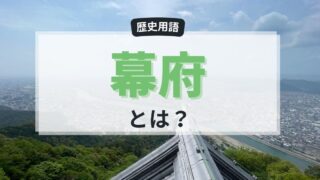 歴史・文化
歴史・文化 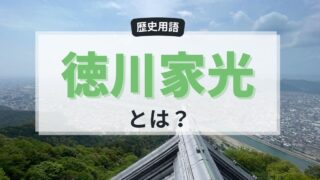 歴史・文化
歴史・文化