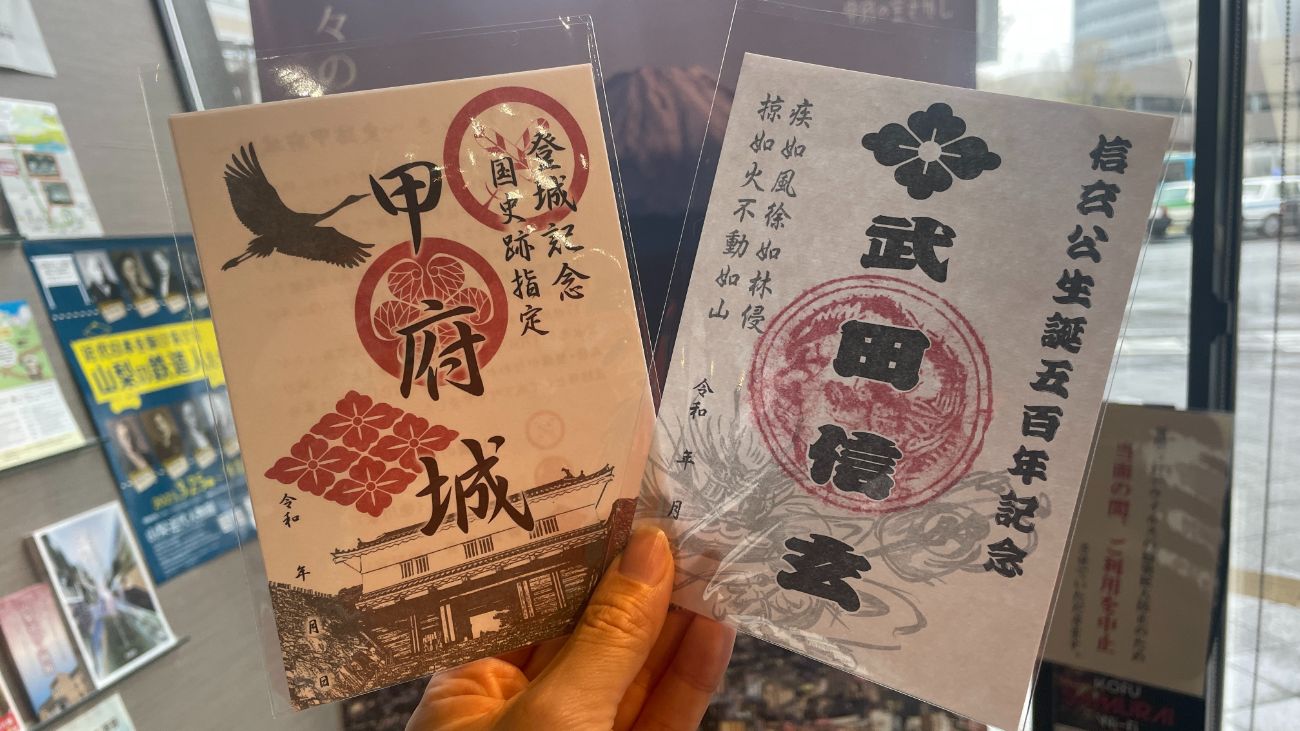日光街道や箱根街道、戸隠古道など、街道の両わきには杉を初めとする木が植えられていることが少なくありません。
古き日本の街道沿いを彩る「杉並木」。
江戸時代に多く植えられたこの並木道は、単なる美しい景観だけでなく、旅人の安全や快適な移動を支える重要な役割を果たしていました。
歴史的な背景とともに、現在も各地に残る杉並木は、多くの観光客を魅了し続けています。
今回は、街道に植えられた杉並木の歴史や、その見どころを分かりやすく解説します。
▼こんな記事もおすすめ!
杉並木とは何か
杉並木(すぎなみき)とは、街道沿いに植えられた杉の木が連なる並木道のことです。
主に江戸時代に整備され、旅人のための目印や日陰を提供する役割を果たしていました。
広大な杉の木が道に沿って並んでいる光景は、壮観でありながら、街道の歴史を感じさせる文化的遺産としても知られています。
杉並木の役割は?日陰や防風の役割を担う

日本における並木の歴史は奈良時代までさかのぼるが、元々は果樹が植えられていました。
夏は日よけになり、喉の渇きや飢えを潤す役割を果たす。並木は行き交う人々を守るために生まれたのです。
杉並木の役割
- 日陰の提供: 杉並木は強い日差しを避け、旅人が暑さをしのげるようにしていました。
- 目印や方向指示: 杉並木は広大な道の中で旅人が迷わないようにする目印の役割を果たしました。
- 防風林: 強風から道や旅人を守るための防風林としても機能しました。
有名な「杉並木」は?
日光街道の杉並木
最も有名な例としては、日光街道の杉並木があります。
この杉並木は、徳川家康を祀る日光東照宮への参拝者を迎えるために植えられたもので、現在でも世界最長の並木道としてギネス世界記録にも認定されています。
箱根街道の杉並木

江戸時代の東海道沿いに植えられた杉並木。
現在でも部分的に残っており、歴史を感じさせる景観を楽しむことができます。
▼そんな箱根街道を歩いてきた様子はこちら!
戸隠神社奥社参道の杉並木

杉並木の参道といえば、長野県では戸隠神社が有名です。
樹齢400年超の杉やシナノキなどが約500メートルに渡って200本以上植えられています。戸隠神社の歴史が2,000年以上であることを考えれば、参道は「杉並木によって最近整備された」ともいえます。
街道の杉並木まとめ

杉並木は、江戸時代の街道文化を象徴する遺産であり、自然と人々の生活が調和した歴史的景観です。
長い年月を経てもなお、訪れる人々に癒しや感動を与える場所として、現在も多くの人々に愛されています。旅の途中で杉並木を通り抜けると、その壮大さと歴史の深さを肌で感じることができるでしょう。
▼宿場・街道のノミチ記事はこちら!