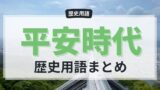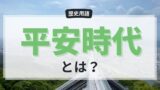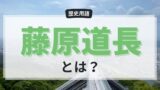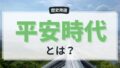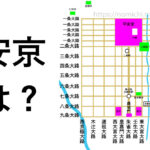平安時代の日本では、天皇が国のトップとして存在していました。
しかし実際に政治を動かしていたのは、藤原氏という貴族たちでした。その仕組みを「摂関政治(せっかんせいじ)」といいます。摂関政治では、天皇がまだ子どものときには「摂政(せっしょう)」が、大人になった天皇には「関白(かんぱく)」がついて政治を行いました。特に藤原道長や藤原頼通の時代には、天皇さえも思い通りにできるほどの権力を握っていました。
今回は、この摂関政治について、中学生でもわかるように簡単に解説していきます。
摂関政治とは、藤原氏が天皇の代わりに政治を行った仕組み
摂関政治(せっかんせいじ)とは、平安時代に藤原氏という有力な貴族が、天皇の代わりに政治を動かした仕組みのことです。
当時の日本では天皇が国のトップでしたが、まだ子どもの天皇や、政治の経験が少ない天皇も多くいました。そこで、天皇の身近に仕えていた藤原氏が、「摂政(せっしょう)」や「関白(かんぱく)」という役職を独占し、実際の政治を自分たちで決めていたのです。
簡単に言うと、「天皇を表のリーダーにして、裏で藤原氏がすべてを動かしていた」状態が摂関政治でした。
摂政とは、子どもの天皇に代わって政治を行う役職
摂政(せっしょう)は、まだ幼い天皇の代わりに政治を行う役職です。
天皇が小さすぎて自分で国のことを決められないときに、「代わりにやりますよ」として政治を動かしました。
最初に摂政になったのは藤原良房(ふじわらのよしふさ)で、ここから藤原氏が政治の世界で強い力を持つようになっていきました。
関白とは、大人の天皇を助けて政治を行う役職
関白(かんぱく)は、天皇が成長して大人になった後でも、天皇のそばで相談役のように振る舞い、実際には政治をリードする役職です。
「助ける」といっても実際には天皇よりも強い影響力を持つことが多く、天皇は名前だけの存在になってしまいました。
藤原基経(ふじわらのもとつね)が最初の関白で、この制度によって藤原氏の力はさらに強くなりました。
藤原氏が摂関政治を行った理由は、天皇家との結びつきを深めるため
藤原氏はなぜこれほどまでに政治の中心になれたのでしょうか?
その理由は「天皇の外戚(母方の親族)」になったからです。
藤原氏は自分の娘を天皇の妻にし、その子どもが天皇になることで、「天皇のおじいちゃん」や「お母さんの実家」として強い立場を築きました。
つまり血のつながりを利用して、自分たちの一族の権力を高めていったのです。
摂関政治の全盛期は、藤原道長と藤原頼通の時代
摂関政治がもっとも力を持ったのは、藤原道長(ふじわらのみちなが)とその息子・藤原頼通(よりみち)の時代です。
藤原道長は「この世をば わが世とぞ思ふ…」という有名な歌を残し、自分の思い通りに政治ができるほどの権力を誇りました。
頼通もその力を受け継ぎ、長い間摂関政治を続けました。この親子の時代は、まさに藤原氏の黄金期といえるでしょう。
摂関政治が終わった理由は、武士の台頭と院政の始まり
摂関政治は100年以上続きましたが、やがて終わりを迎えます。
その理由は、武士の力が強くなったことと、院政(上皇が行う政治)が始まったことです。
平安時代の後半になると、武士が地方で力を持ち、藤原氏よりも現実的な力を発揮するようになりました。また、白河上皇が「院政」を始め、天皇の親である上皇が直接政治を行うようになったため、藤原氏の立場は弱まっていきました。
まとめ:摂関政治とは、藤原氏の権力を示す政治の仕組み
- 摂関政治とは、藤原氏が摂政・関白として天皇の代わりに政治を行った仕組み。
- 摂政=子どもの天皇の代理、関白=大人の天皇の相談役。
- 藤原氏は天皇と親族関係を結ぶことで力を拡大。
- 藤原道長・頼通の時代がピークだった。
- 武士の台頭と院政の登場で衰退した。
中学生の歴史テストでは「摂関政治=藤原氏が力を握った政治」と書ければ十分です。
でも、背景まで理解しておくと、院政や武士の登場とのつながりも見えてきて、歴史の流れがぐっとわかりやすくなります!
▼歴史用語の記事はこちら!