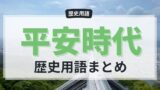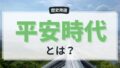「院政(いんせい)」とは、天皇が退位したあとに「上皇(じょうこう)」となり、政治の実権を握る政治の仕組みです。
それまでの日本では、天皇が直接政治を行うのが基本でしたが、平安時代の後半になると、天皇をやめた上皇が「院」と呼ばれる御所に移り、そこで政務を行うようになりました。これが「院政」です。
院政を始めたのは 白河天皇(しらかわてんのう)で、1086年に譲位(天皇の位を譲ること)してから本格的に始まりました。院政はその後、鎌倉時代のはじめまで続き、日本の政治の大きな特徴の一つとなりました。
なぜ院政が始まったのか?
院政が始まった背景には、いくつかの理由があります。
藤原氏の摂関政治を抑えるため
平安時代中期までは、藤原氏が娘を天皇の后に入れて「外戚(母方の親戚)」となり、摂政・関白として政治を独占していました。
しかし、白河天皇は藤原氏の力を弱め、自分の思うように政治を行いたいと考えました。そこで「天皇をやめても上皇として政治をする」という形を作り出したのです。
天皇の若年退位
天皇は幼くして即位することも多かったため、実際の政治は上皇や摂関が行うことが多くなりました。上皇が実権を持つことで、政治が安定したのです。
白河上皇と院政のはじまり
白河天皇は、1086年に息子の堀河天皇に位を譲り、自らは「上皇」となりました。これが院政のはじまりです。
白河上皇は特に強力な権力を持ち、「院庁(いんのちょう)」という役所を設けて政治を行いました。貴族や武士を取り込みながら、自らの意志で国政を動かしていったのです。
さらに、白河上皇の時代には、武士の力が台頭してきました。特に「源氏」や「平氏」などの武士団が院政を支えるようになり、これが後の武士政権成立へとつながっていきます。
鳥羽上皇・後白河上皇と院政の発展
白河上皇のあとを継いで、鳥羽上皇や後白河上皇も院政を行いました。
なかでも 後白河上皇 は、日本史において非常に重要な存在です。
- 保元の乱(1156年)、平治の乱(1159年)といった大きな内乱を経験
- 平清盛と手を組んで平氏政権を成立させた
- その一方で平氏の台頭を恐れ、源氏とも結びついた
このように、後白河上皇は時代を大きく動かした人物でした。
院政と武士の台頭
院政の時代には、武士の力が強まったことも特徴です。
上皇は、自らの権力を維持するために「北面の武士(ほくめんのぶし)」と呼ばれる私的な武士団を組織しました。これによって、朝廷の政治に武士が深く関わるようになり、後の武家政権の基盤が作られたのです。
特に平清盛は後白河上皇の信任を得て、平氏の力を大きく伸ばしました。やがて平氏政権が誕生するのは、この院政時代の流れの中で起こったことでした。
院政の終わりとその影響
院政は、鎌倉時代に入っても続きましたが、源頼朝による鎌倉幕府の成立によってしだいに弱まりました。武士が実際の政治を担うようになると、上皇の権力は次第に形骸化していきます。
しかし、院政がもたらした影響は大きく、
- 摂関政治から武家政権への移行を助けた
- 武士が中央政治に登場するきっかけを作った
- 後白河上皇など強い個性を持つ上皇が時代を動かした
といった点で、日本史の重要な転換期となりました。
まとめ|院政とは「上皇による新しい政治の形」
院政とは、天皇が退位したあとに上皇として政治を行う仕組みで、白河上皇から始まりました。摂関政治を抑えるために誕生し、武士の台頭や平氏の政権成立など、日本の歴史を大きく動かしました。
中学生や高校生にとっては、
- 「院政=上皇の政治」
- 「始めたのは白河上皇」
- 「武士の台頭と深く関係」
この3つを押さえれば、入試でも役立ちます。
院政は、貴族社会から武士の時代へ移り変わる橋渡しの時期として、とても重要な政治制度だったのです。
▼歴史用語記事はこちら!