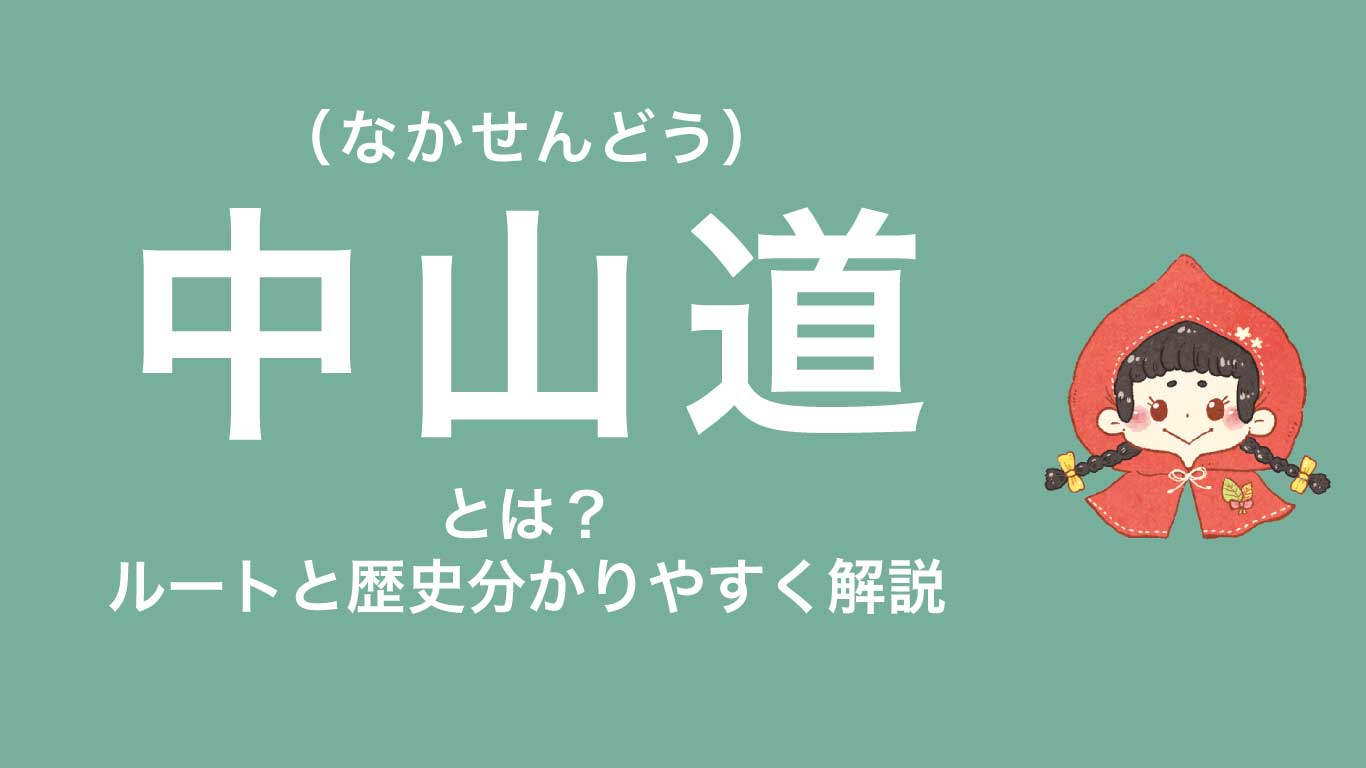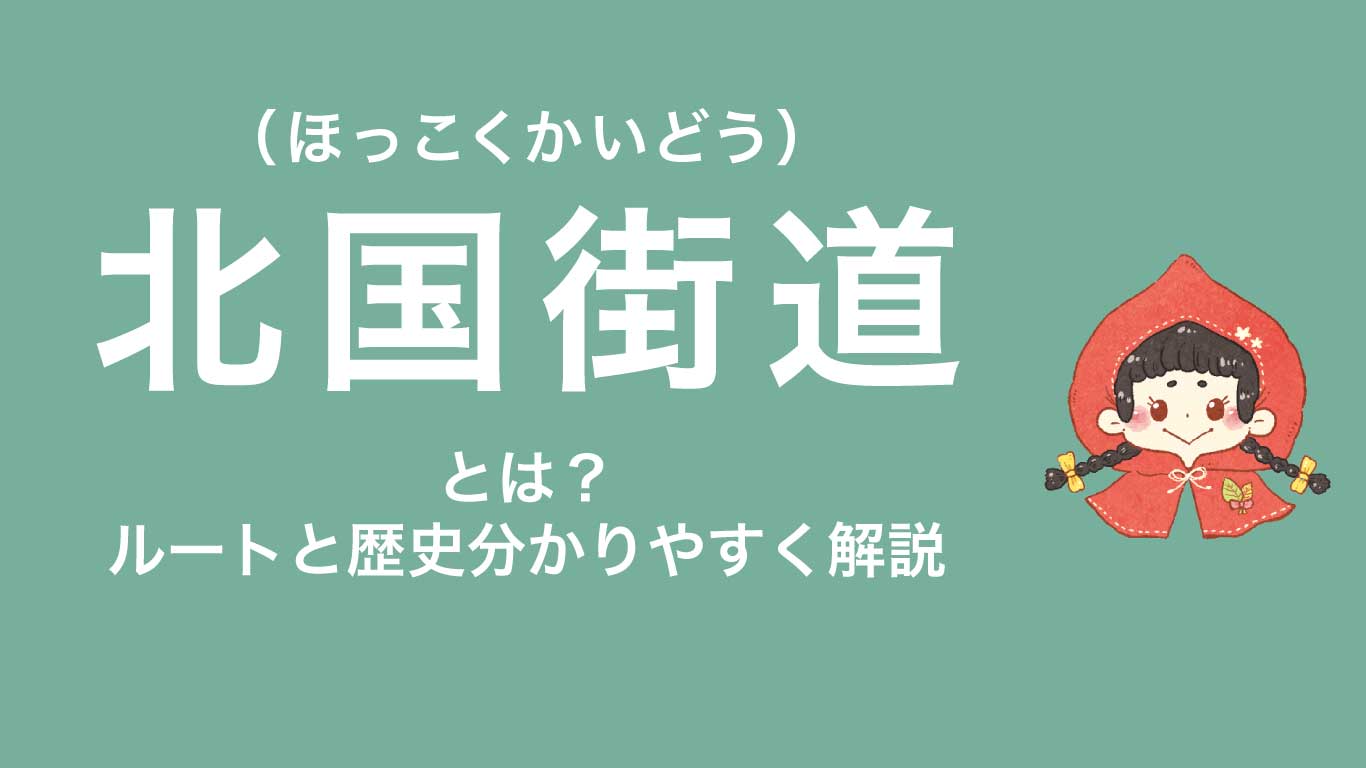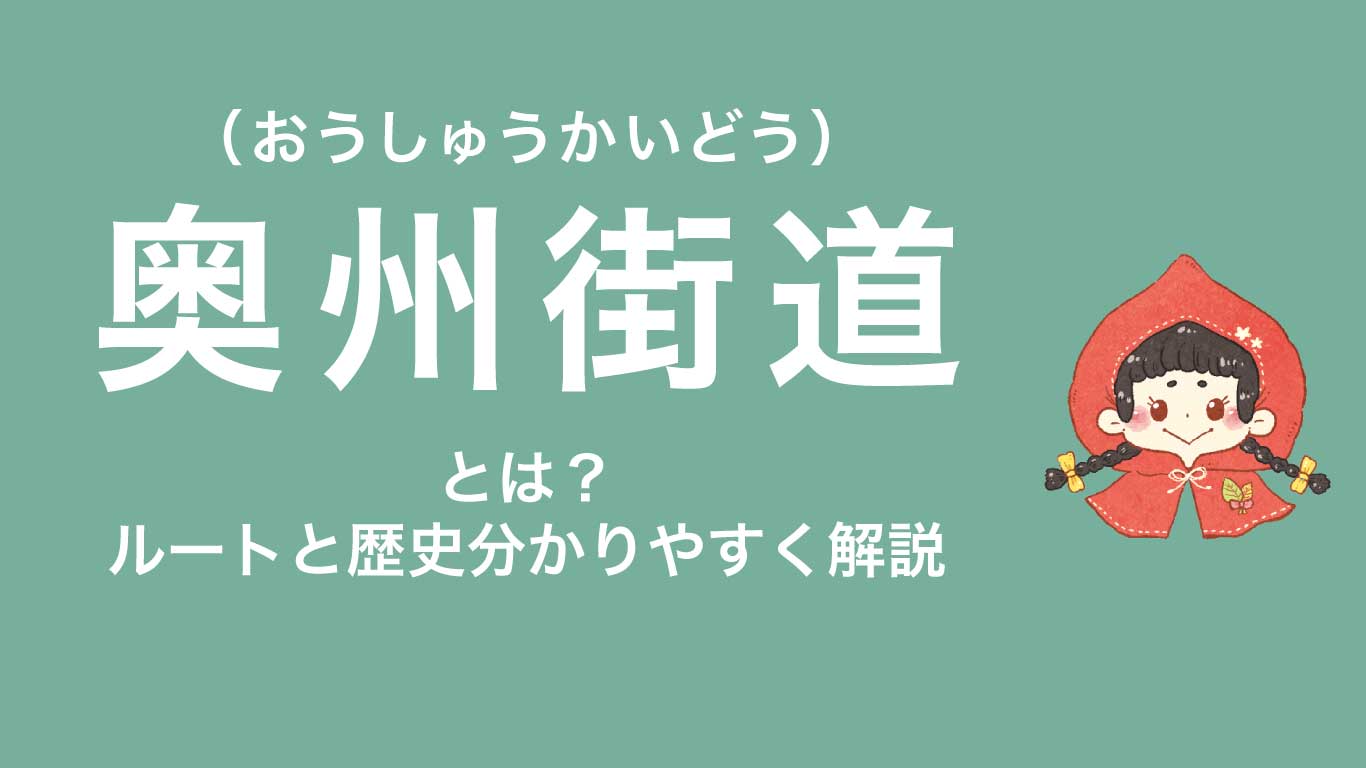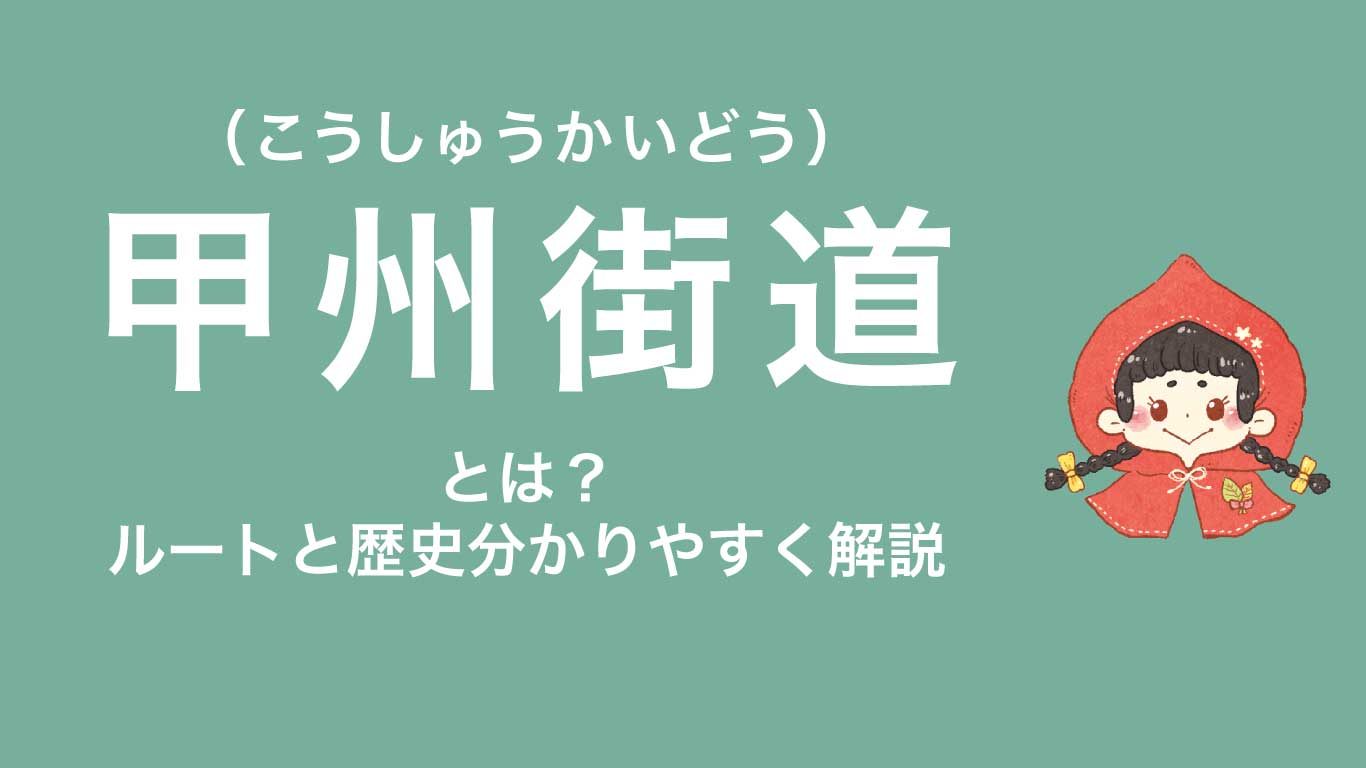旅の途中で大きな川に行き当たったとき、もし橋がなかったらどうするでしょうか。
現代なら車や鉄道で簡単に渡れますが、江戸時代の人々にとってはそうはいきませんでした。
その時に欠かせなかったのが「渡し場(わたしば)」です。
渡し場は人や荷物を川の向こうへ運ぶための拠点であり、街道の交通を支える大切な役割を果たしていました。本記事では、渡し場の仕組みや歴史的背景、有名なエピソードまで、初心者にもわかりやすく解説します。
渡し場(わたしば)とは?川や湖などの水域を渡るために設けられた場所

渡し場(わたしば)とは、川や湖などの水域を渡るために設けられた場所のことです。
橋が整備されていない時代、大きな川を越えるには渡し船や筏(いかだ)が欠かせませんでした。旅人が行き交う街道沿いには必ず渡し場があり、人々や物資の流通を支える交通の要所となっていました。
江戸時代に整備された五街道にも数多くの渡し場が存在し、なかでも東海道の「大井川の渡し」は特に有名です。川を渡る際には通常の宿泊料や通行料とは別に「川越し料」と呼ばれる追加料金が必要で、旅人の大きな出費のひとつでした。
江戸時代における渡し場の役割
江戸時代は、徳川幕府の政策によって街道が整備されましたが、大きな川にはあえて橋がかけられないことがありました。
これは軍事的な理由によるものです。橋があれば大軍が一気に江戸へ攻め込む可能性があるため、防衛上の観点から渡し船に頼らざるを得ない場所が残されました。
そのため渡し場は単なる交通手段ではなく、幕府の意図を反映した戦略的な拠点でもあったのです。旅人にとっては避けて通れない場所であり、川止めによって足止めされることも珍しくありませんでした。
有名な渡し場とエピソード

東海道の大井川は、江戸時代の旅人にとって最大の難所のひとつでした。
増水すると川を渡ることができず、多くの人々が川の手前の宿場で数日間も足止めを食らいました。この「川止め」が宿場の経済を潤す一方で、旅人にとっては出費や時間の負担となりました。
また、渡し船を担ったのは地元の渡し守や人足(にんそく)たちで、彼らが旅人の荷物を抱えて川を渡す光景は、浮世絵や紀行文にも多く描かれています。旅の安全を担った存在として、渡し場の人々は江戸時代の交通文化を象徴する役割を果たしました。
渡し場と現代の名残

明治以降になると鉄道や近代的な橋が整備され、渡し場の多くは姿を消しました。
しかし現在でも、一部地域では観光用や地域交通として渡し船が運行されており、歴史の名残を体験することができます。
例えば、東京の隅田川や京都の宇治川などには渡し船が残され、江戸時代の旅人気分を味わうことができます。こうした場所を訪れると、当時の街道を歩いた人々の苦労や生活に思いを馳せることができるでしょう。
まとめ|渡し場(わたしば)とは?江戸時代の交通を支えた重要な拠点

渡し場は、江戸時代の交通を支える重要な拠点であり、橋がなかった時代に人々の旅や物流を可能にしました。
特に大井川の渡しは旅人の記憶に残る難所で、街道の歴史を語るうえで欠かせない存在です。現代の私たちにとっては、渡し場の跡地や渡し船を訪ねることで、江戸時代の旅の雰囲気を身近に感じられる貴重な文化遺産といえるでしょう。
▼街道用語解説記事はこちら!