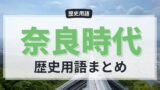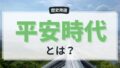奈良時代(ならじだい)は、日本の歴史の中で710年から794年までの約80年間を指します。
都が奈良の平城京に置かれたことから「奈良時代」と呼ばれています。この時代は、中国の制度を取り入れた律令国家の仕組みが整い、中央集権的な政治が行われました。また、仏教が国家的に重視され、国分寺や東大寺の建立、大仏の造立などが進められました。国際交流も盛んで、シルクロードを通じた文物が伝わり、国際色豊かな「天平文化」が花開いた時代です。
本記事では、奈良時代の政治・社会・文化をわかりやすく解説します。
奈良時代とは?基本概要
奈良時代は710年、元明天皇が都を藤原京から平城京へ遷したことで始まります。
平城京は唐の都・長安をモデルに造られた本格的な都で、碁盤の目のように道が整備され、中央には天皇が住む宮殿(大内裏)が置かれました。
この都を中心に、律令国家の政治が進められ、仏教を中心とした文化も大きく発展しました。794年、桓武天皇が平安京へ遷都するまでの約80年間が奈良時代です。
奈良時代の政治と律令制度
律令国家の仕組み
律令とは「律=刑法」「令=行政法」を指し、奈良時代は律令に基づいた国家運営が行われた時代です。
中央政府は天皇を頂点とし、二官八省(にかんはっしょう)と呼ばれる役所が政治を担当しました。
二官八省と中央集権体制
二官とは、政治全般をつかさどる太政官(だいじょうかん)と、神道儀礼をつかさどる神祇官(じんぎかん)のこと。
八省は現在の省庁にあたるもので、財政や軍事、宮中の運営などを担当しました。これにより中央集権体制が確立し、地方にも国司や郡司が派遣されて国を管理しました。
班田収授法と土地制度
農民は戸籍と計帳によって把握され、6歳以上の男女に口分田(くぶんでん)が割り当てられました。
この制度を班田収授法と呼びます。農民は与えられた田で農業を行い、租庸調(そようちょう)と呼ばれる税を負担しました。
三世一身法・墾田永年私財法
しかし、人口が増え続ける一方で土地が不足し、班田収授法は次第に行き詰まります。
そこで723年には「三世一身法(さんぜいっしんのほう)」が制定され、開墾した土地を三代にわたって私有できるようになりました。さらに743年の「墾田永年私財法」によって、開墾地は永久に私有できることが認められ、荘園(しょうえん)が発展していくきっかけとなりました。
奈良時代の社会と人々の暮らし
農民の生活と税の負担
農民の暮らしは厳しいものでした。田を耕して得た収穫から、米を納める「租」、布を納める「庸」、地方の特産物を納める「調」を負担しなければなりませんでした。
また、防人(さきもり)として九州の防衛に派遣されることもありました。
戸籍と計帳による管理
国家は戸籍と計帳によって農民を把握し、口分田を分配しました。
この仕組みは、律令国家が国民一人ひとりを支配する基盤でしたが、人口の変動や逃亡農民の増加によって制度は次第に機能しなくなっていきました。
都市と地方の生活
平城京では役人や貴族、商人が暮らし、唐から伝わった文物や仏教文化が花開きました。一方で地方の農民は質素な生活を送り、税の負担に苦しむことが多く、身分の格差は大きなものでした。
奈良時代と仏教の広がり
聖武天皇と鎮護国家思想
奈良時代を代表する天皇が聖武天皇です。疫病や飢饉、反乱が相次ぐ中、聖武天皇は「仏教の力で国を守る」という鎮護国家(ちんごこっか)の思想を打ち出しました。
国分寺・国分尼寺の建立

741年、聖武天皇は全国に国分寺と国分尼寺を建てるよう命じました。これによって仏教が全国に広まり、国家の統治と結びついていきました。
東大寺の大仏造立

奈良時代の象徴ともいえるのが東大寺の大仏です。
752年、盧舎那仏(るしゃなぶつ)の開眼供養が行われ、国内外から多くの人々が集まりました。大仏建立は国家事業であり、仏教が国家の中心に位置づけられたことを示しています。
光明皇后と福祉活動
聖武天皇の皇后である光明皇后は、仏教に基づき貧しい人や病人を救済する施薬院(せやくいん)や悲田院(ひでんいん)を設立しました。光明皇后は慈悲深い人物として後世に伝えられています。
奈良時代の文化と国際交流
天平文化の特徴
奈良時代を代表する文化は「天平文化(てんぴょうぶんか)」と呼ばれます。
仏教を中心としながらも、シルクロードを通じた国際色豊かな文化が取り入れられました。
正倉院の宝物とシルクロード文化
東大寺の正倉院には、シルクロードを通じて伝わったガラス製品や楽器、織物などが収められています。
これらは奈良時代が国際的な交流の時代であったことを物語っています。
遣唐使と国際交流
遣唐使によって唐の最新の制度や文化が日本に伝えられました。
仏教の戒律を伝えた鑑真(がんじん)が日本に来たことも大きな出来事です。鑑真は唐招提寺(とうしょうだいじ)を建て、日本の仏教発展に大きく貢献しました。
奈良時代の代表的な人物
- 聖武天皇:東大寺の大仏を建立した天皇。
- 光明皇后:仏教を信仰し、福祉活動に尽力した皇后。
- 行基:民衆に仏教を広め、大仏建立にも尽力した僧。
- 鑑真:唐から来日し、日本に戒律を伝えた高僧。
奈良時代の終わりと平安時代への移行
奈良時代の後半になると、荘園の増加や農民の逃亡が相次ぎ、律令制度は形骸化していきます。
こうした混乱を収めるため、794年に桓武天皇は平安京に都を移しました。これにより、奈良時代は幕を閉じ、平安時代へと移っていきます。
まとめ|奈良時代とは?律令国家と仏教文化をわかりやすく解説
奈良時代は、律令制による国家運営が整い、仏教が国家と深く結びついた時代でした。
平城京を中心に政治・文化が発展し、遣唐使やシルクロードを通じた国際交流も盛んに行われました。その一方で、税負担の重さや土地制度の崩壊など、社会の矛盾も表面化しました。
奈良時代は日本の古代国家の完成期であり、後の平安時代や中世社会の基盤を形づくった重要な時代といえるでしょう。
▼歴史用語のノミチ記事はこちら!