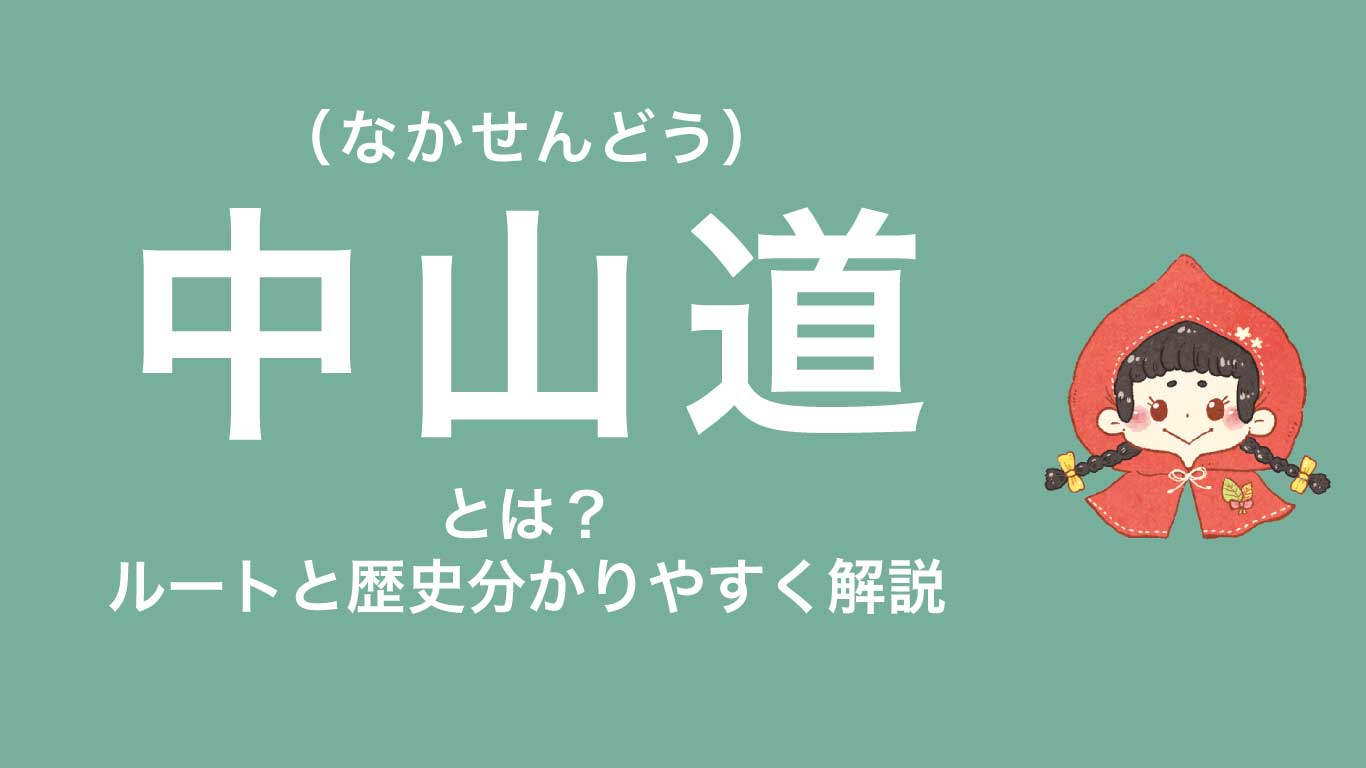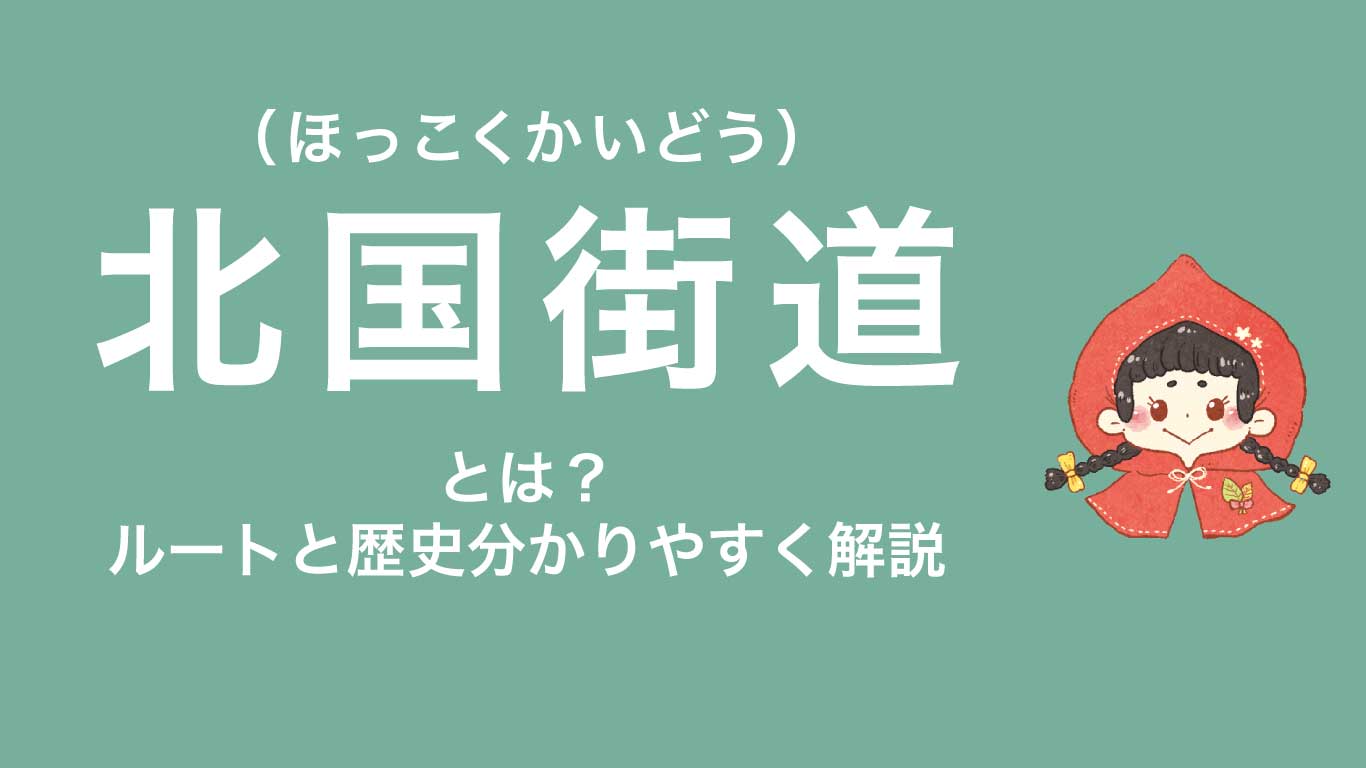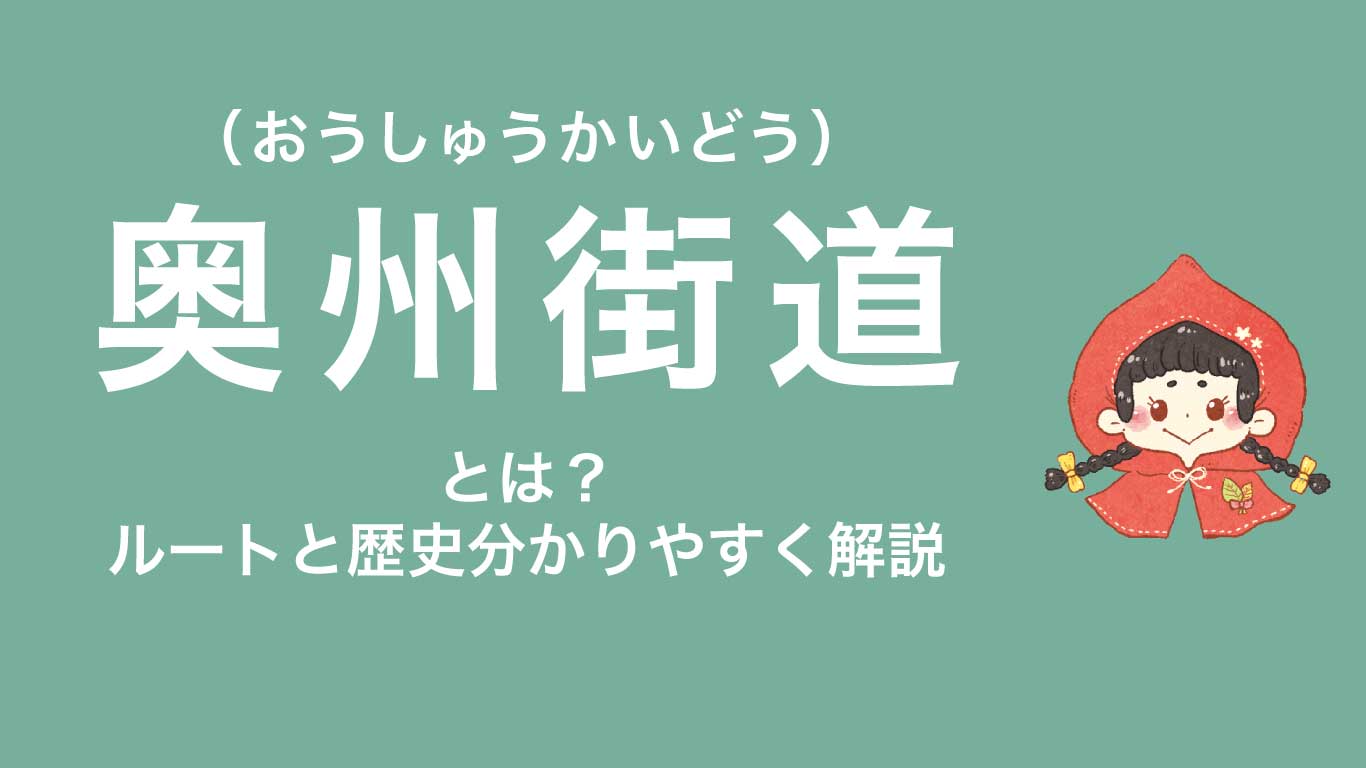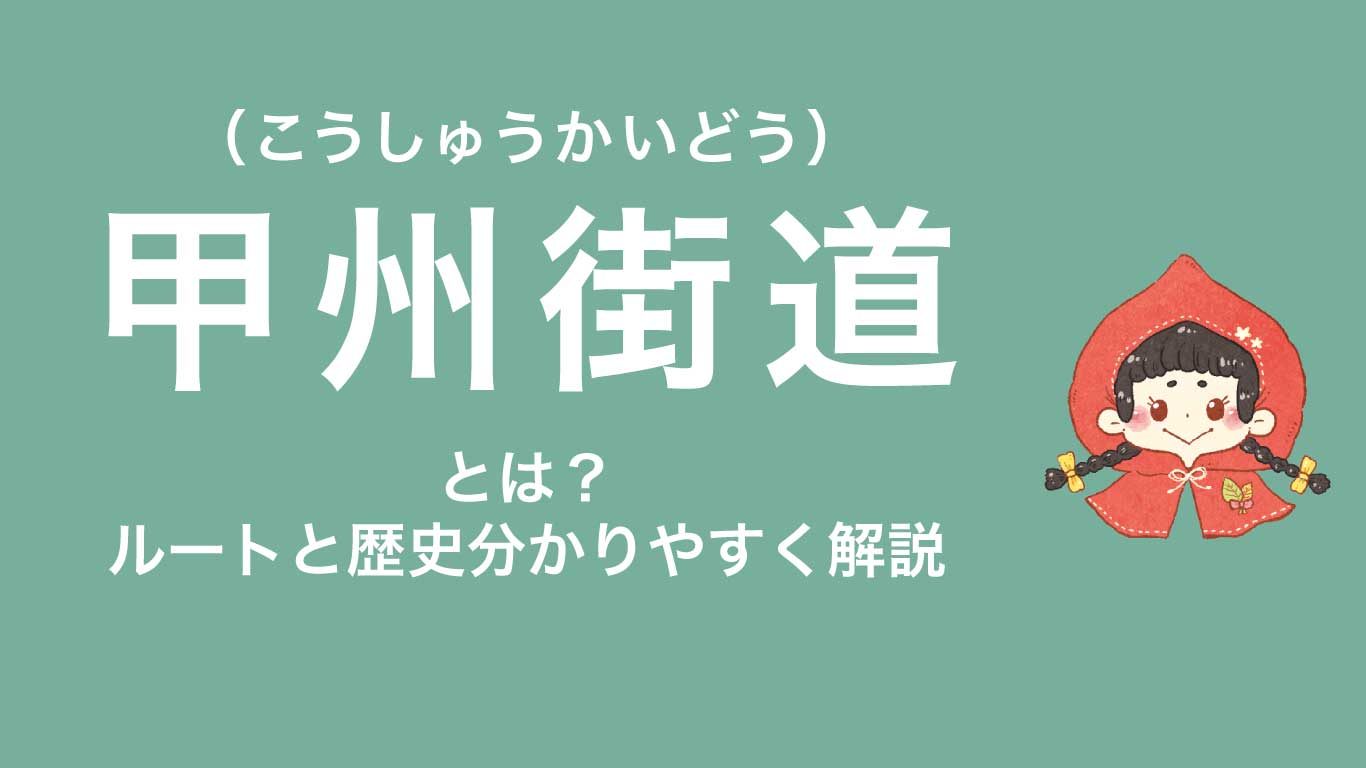旅の途中、分かれ道で道に迷ったことはありませんか?
現代のような地図アプリも案内板もない頃、道案内の頼りになるのが「道標(どうひょう/みちしるべ)」でした。
道標は、分岐点や街道の辻、山道、峠などに設置され、目的地までの方向や距離を知らせて旅人を導いていました。江戸時代、街道を歩く旅の風景には、必ずと言っていいほどこの道標があったのです。
本記事では、道標がどのような意味を持っていたか、どこで見られるのか、そして現代の散策でどのように楽しめるかをわかりやすく紹介します。
道標とは?意味と言葉の由来
「道標」という言葉は、「道」を案内する「標(しるし)」という意味で、訓読みでは「みちしるべ」、音読みでは「どうひょう」と読みます。どちらも、通行する人々が道を見失わないように方向や距離を示した標識です。
この概念自体はかなり古くから日本にあり、寺社参詣道、街道、山道など、生活や信仰、物資の流通のための道が人々に利用されていた場所に設置されてきました。
道標の設置場所と種類

道標は以下のような場所に設置されることが多いです。
- 街道や街道の分岐点(追分・辻)
- 宿場町の入口や中心部
- 山道・峠道・合流点
- 神社や仏閣への参道入り口
形状や素材、表示内容にもバリエーションがあります。
- 石造の角柱型のもの
- 塚や基壇を備えたもの
- 地蔵や馬頭観音などを兼ねたもの、祠と一体になっているもの
- 距離を「里(り)」や「丁(ちょう)」で示したもの
- 「右○○道」「左△△道」などの方向案内を刻んだもの
江戸時代における道標の役割

江戸時代の交通事情を理解すると、道標がどれほど重要だったか見えてきます。
- 旅人・物資の流通を助ける:道標があることで、初めての道でも安心して進むことができた
- 宿場町との結びつき:宿場を目指す旅人が、道標で方向を確かめて宿を探した
- 地域の信仰や文化との重なり:山岳信仰のルート、寺社への参詣道での道案内としての設置が多かった
- 距離感の共有:「里程(里数)」が刻まれ、道中の旅の負担や時間を測る基準となった
また、道標が設置される場所や数の多さは、その道がどのくらい往来が多かったかを示す指標ともなります。
有名な道標の例

いくつかの地域で保存・展示されていて見どころになる道標を紹介します。
- 関東・埼玉県入間市の「日光脇往還と甲州往還が交わる追分の道標」:交差する街道の合流点に立ち、山岳信仰の霊山名なども刻まれている。
- 北国街道沿い(長野県など)で見られる追分道標:中山道や北国街道の分岐を示すもの。
- 大阪市東成区の「暗越(くらがり)奈良街道」の道標:距離や行先が刻まれ、夜間に火袋(灯り)が設けられていたものもある。
道標と街道歩き・古道散策との関係

現在、古道歩きや街道散策をする人にとって道標は、「当時の旅人が見た風景」を垣間見る鍵です。道標を見ることで、街道がどう続いていたのか、どこが主要な分岐点だったのか、また旅のルートがどのように人々の生活に関わっていたかを感じることができます。
散策中には、地図と照らし合わせて「この道標は○○へ向かう道か」「ここがかつての追分だったのか」などを考えると、旅の楽しさが増します。
道標を探すヒントと見どころ
街道遺産として道標を巡る際のポイント。
- 古い地図をチェックする:現在の道と重なる街道ルートが載っている地図で、道標の設置位置を推定できる
- 近くの寺社や宿場町を訪れる:街道の宿場町には必ずと言っていいほど道標の跡か復元があることが多い
- 表示内容を読む:刻まれた文字(行先・里数・山名・寺名など)は、地域の歴史を知る手がかりになる
- 状態をよく見る:摩耗や文字の消えかけた道標は、どれだけ往来があったかを物語っている
まとめ|道標とは?江戸時代の“道しるべ”!歴史と見どころもご紹介
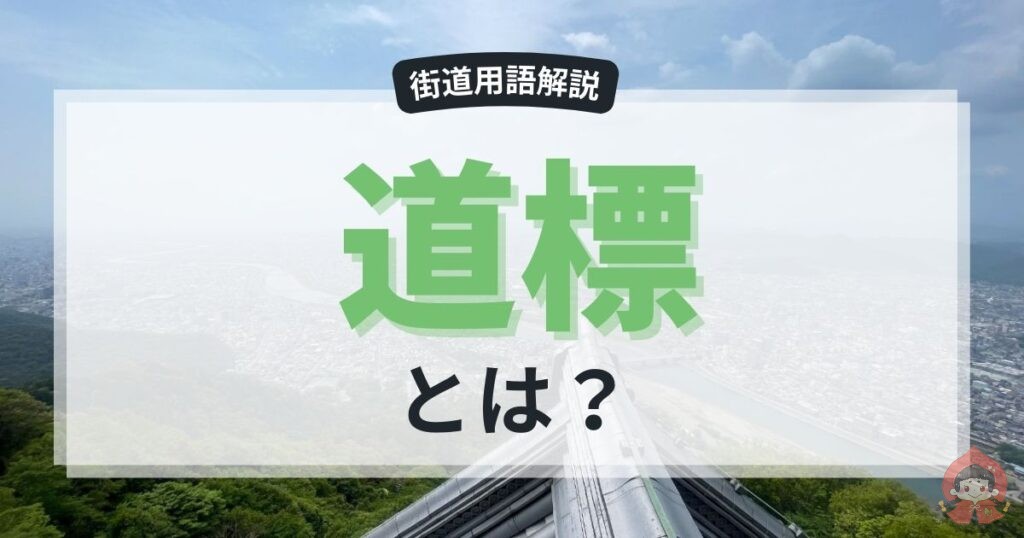
道標は、江戸時代の旅や生活に欠かせない「目印」であり、道案内板の原点とも言えます。
街道や古道を歩くとき、道標を見ることは、ただ場所を知る以上の意味があります。当時の人々の道に対する考え方、地域間の関係性、旅の苦労と工夫など、多くを教えてくれる存在です。
古道を歩く旅を計画するなら、道標を探して歩いてみることをおすすめします。道標が残っていれば、旅が豊かな学びの体験にもなります。
▼街道宿場用語の記事はこちら!