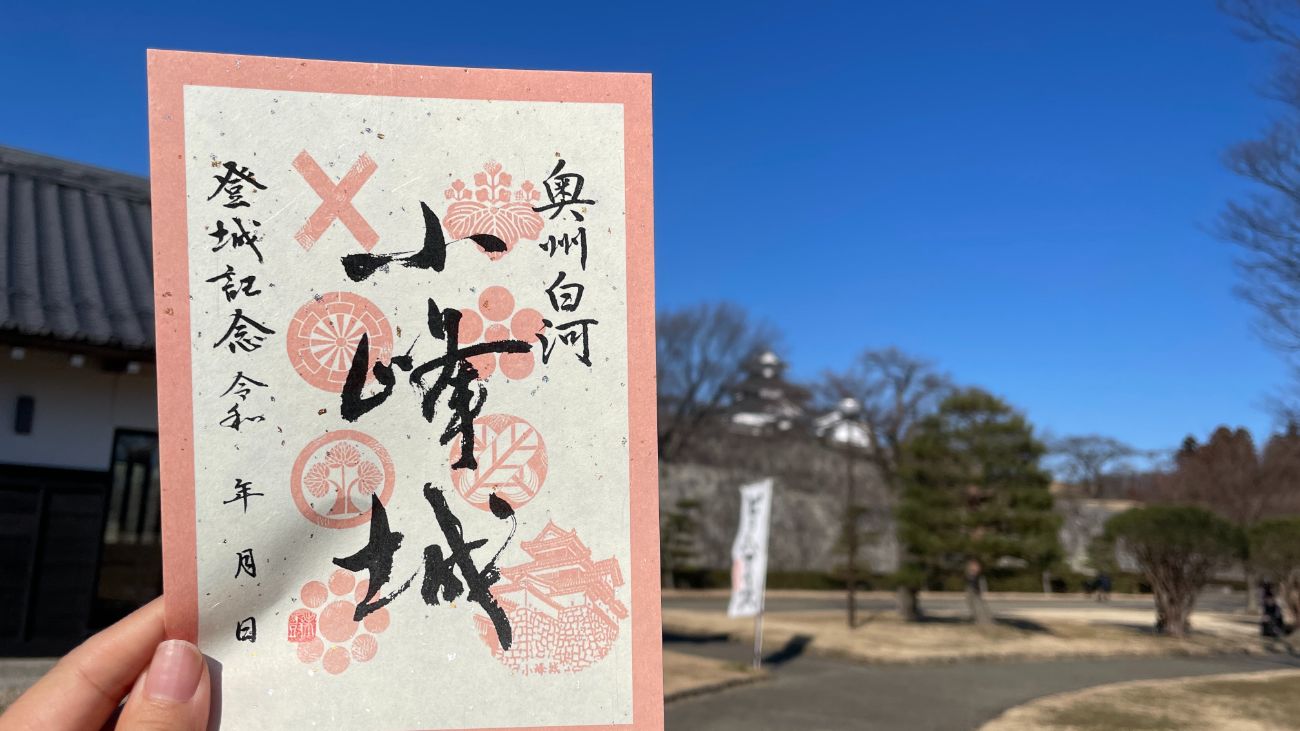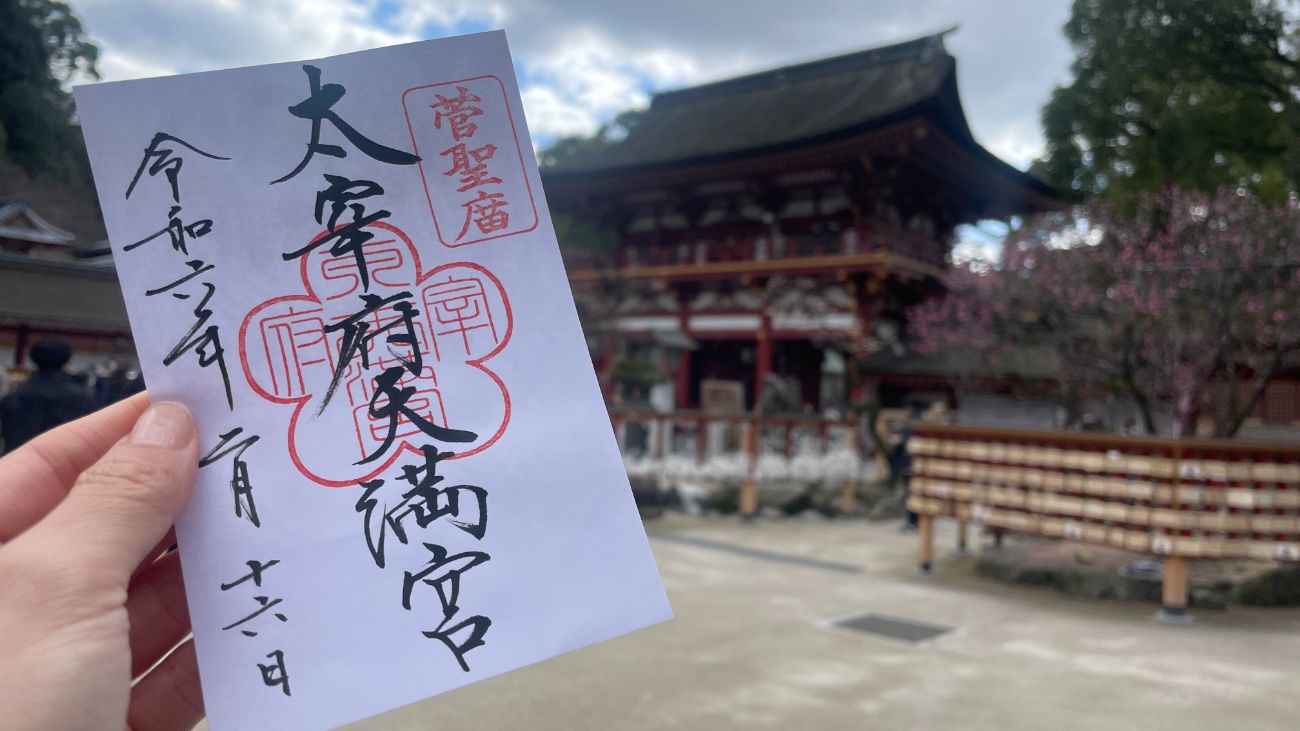1人あたりの鮭の消費量が日本一、「鮭のまち」として知られる新潟県村上市。
“鮭のまち”として全国的に知られ、鮭とともに暮らす文化が1000年以上も続いています。秋になると市内を流れる三面川(みおもてがわ)には鮭が遡上し、まちの至るところでつるし干しされた塩引き鮭が風に揺れます。
今回は、村上鮭の歴史や伝統漁法、そして地元の名店「井筒屋」で味わえる鮭料理をご紹介します。
村上はなぜ“鮭のまち”になったのか

村上市の鮭文化の中心にあるのが三面川です。
三面川は阿賀野川の支流で、豊かな水量と清流を誇り、鮭の自然遡上に最適な環境を備えています。平安時代にはすでに朝廷への献上品として村上の鮭が知られており、『延喜式』にもその名が記されています。
村上藩時代には、鮭は年貢や財源として重要な役割を果たし、領民にとって生活を支える恵みそのものでした。こうして“鮭とともに生きるまち”という独自の文化が根づいていきます。
1000年受け継がれる村上鮭の伝統漁法「居繰網漁(いぐりあみ)」
村上鮭漁の解禁は毎年秋。
特に注目されるのが、江戸時代から続く「居繰網漁(いぐりあみ)」です。これは川を横切るように網を張り、遡上してくる鮭を捕える漁法。産卵前の鮭を捕りすぎないよう配慮し、翌年以降の資源を守るサステナブルな仕組みでもあります。
村上では、こうして獲れた鮭を「塩引き鮭」や「鮭の酒びたし」に加工し、冬の保存食として活用してきました。鮭の命を余すところなく使い切る姿勢は、漁師町ならではの知恵です。
村上藩を救った「青砥武平次」とは
江戸時代中期、村上藩の財政は深刻な赤字に陥っていました。
藩士・青砥武平次は三面川の鮭を保護し、産卵期以外は禁漁とする「種川の制」を考案。翌年以降の鮭の漁獲量が飛躍的に増え、藩の財政を立て直しました。この制度は“日本初の自然保護政策”ともいわれ、村上鮭文化の礎となりました。
村上鮭の保存食と郷土料理

村上鮭の代表格といえば塩引き鮭。新鮮な鮭を一本丸ごと塩で漬け込み、冬の寒風にさらしてじっくり干し上げることで、旨みと香りが凝縮されます。切り身を焼けば、香ばしい皮とふっくらとした身が口いっぱいに広がります。
もう一つの名物が「鮭の酒びたし」。塩引き鮭をさらに半年以上干し、薄く削って日本酒に浸して食べる珍味です。ほかにも、氷頭(ひず)なます、はらこ(イクラ)の醤油漬け、内臓を使った味噌漬けなど、まさに“鮭を余すことなくいただく”のが村上流です。
村上鮭を味わう!井筒屋

鮭料理を存分に味わいたいなら、創業100年以上の老舗「井筒屋」がおすすめです。地元の鮭をふんだんに使った「村上鮭づくし御膳」は、塩引き鮭、酒びたし、はらこ飯、氷頭なますなど、村上の鮭文化を一度に堪能できる豪華な内容。

店内は落ち着いた和の雰囲気で、観光客だけでなく地元の人々にも愛されています。お土産コーナーでは、自家製の塩引き鮭や鮭加工品も購入可能。村上観光のランチやディナーにぴったりの一軒です。

まとめ|1000年の歴史を誇る“鮭のまち”村上へ
村上鮭は、単なるご当地グルメではなく、1000年もの歴史と人々の暮らしが息づく文化そのものです。秋の鮭漁解禁時期や冬のつるし干しシーズンは特に見応えがあり、地元料理店での食事とセットで訪れたい場所。
鮭好きはもちろん、歴史や伝統文化に興味のある人にも、村上は必ず心に残る旅先となるはずです。
▼おすすめのノミチ記事はこちら